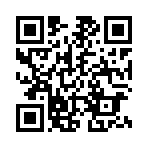2011年09月25日
(読書メモ) 川崎発 子どもの権利条例
自己流読書メモです

「川崎発 子どもの権利条例」
子どもの権利条約 総合研究所編 編集 協力:川崎市
2002年エイブル研究所発行
■概要■
1:逐条解説
「川崎市子どもの権利に関する条例」
2:条例で何が変わるか
「理念と権利保障」「子どもの参加の権利」「子どもからの相談と権利救済」
「子どもの権利に関する行動計画と保障状況の検証」「オンブズパーソン制度」
3:市民参加型条例のこれまでとこれから
「地域教育会議」「市民サロン」「子ども委員会」
4:動き始めた川崎
「川崎市子ども会議(準備会)」「川崎子ども夢パーク」「学校教育推進会議」
「川崎市子どもの権利委員会」
5:資料
「川崎市子どもの権利に関する条例」「川崎市人権オンブズパーソン条例」
「学校教育推進会議・指針・他」「川崎市子どもの権利委員会規則・運営要領」
おまけ 所感
===========================
 1:逐条解説
1:逐条解説
【川崎市子どもの権利に関する条例】抜粋
<前文>
・ 「子ども観」「子どもの権利の理念」の考え方の違いを克服
・ 子どもを「保護される対象」から「自ら権利を行使する主体」へと転換
・ 子どもは権利について学習し、実際に行使することを通して権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任を身につける。
→権利の相互尊重によって「権利と責任(と義務)」の考え方を整理

「川崎発 子どもの権利条例」
子どもの権利条約 総合研究所編 編集 協力:川崎市
2002年エイブル研究所発行
■概要■
1:逐条解説
「川崎市子どもの権利に関する条例」
2:条例で何が変わるか
「理念と権利保障」「子どもの参加の権利」「子どもからの相談と権利救済」
「子どもの権利に関する行動計画と保障状況の検証」「オンブズパーソン制度」
3:市民参加型条例のこれまでとこれから
「地域教育会議」「市民サロン」「子ども委員会」
4:動き始めた川崎
「川崎市子ども会議(準備会)」「川崎子ども夢パーク」「学校教育推進会議」
「川崎市子どもの権利委員会」
5:資料
「川崎市子どもの権利に関する条例」「川崎市人権オンブズパーソン条例」
「学校教育推進会議・指針・他」「川崎市子どもの権利委員会規則・運営要領」
おまけ 所感
===========================
 1:逐条解説
1:逐条解説【川崎市子どもの権利に関する条例】抜粋
<前文>
・ 「子ども観」「子どもの権利の理念」の考え方の違いを克服
・ 子どもを「保護される対象」から「自ら権利を行使する主体」へと転換
・ 子どもは権利について学習し、実際に行使することを通して権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任を身につける。
→権利の相互尊重によって「権利と責任(と義務)」の考え方を整理
===========================
 1:逐条解説
1:逐条解説
【川崎市子どもの権利に関する条例】抜粋
<前文>
・ 「子ども観」「子どもの権利の理念」の考え方の違いを克服
・ 子どもを「保護される対象」から「自ら権利を行使する主体」へと転換
・ 子どもは権利について学習し、実際に行使することを通して権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任を身につける。
→権利の相互尊重によって「権利と責任(と義務)」の考え方を整理
<第一章 総則>
・子ども・・・18歳未満
<第三条 責任>
・ 市は子どもの権利を尊重し、その保障に努める。
・ 市民は、子どもの権利が保障されるよう市との協働に努めなければならない。
・ 育ち学ぶ施設の設置者、管理者、職員は市の施策に協力するよう努めるとともに、施設における子どもの権利が保障されるよう努めねばならない。
・ 事業者は、市の施策に協力するよう努めねばならない。
<第七条 学習等への支援等>
<第二章 人間として大切な子どもの権利>
・ 安心して生きる権利
・ ありのままの自分でいる権利
・ 自分を守り、守られる権利
・ 自分を豊かにし、力づけられる権利
・ 自分で決める権利
・ 参加する権利(意見表明の権利)
・ 個別の必要に応じて支援を受ける権利(差別の禁止)
<第三章 家庭・育ち学ぶ施設及び地域における子どもの権利の保障>
<第一節 親等による子どもの権利の保障>
・ 親は養育の支援を受けることができる
・ 親等・・・虐待及び体罰の禁止
・ 市の努力義務・・・虐待からの救済及びその回復
<第二節 育ち学ぶ施設における子どもの権利の保障>
・ 環境整備、安全管理体制整備の努力義務
・ 虐待及び体罰の禁止
・ 救済と回復の努力義務
・ いじめの防止の努力義務
<第三節 地域における子どもの権利の保障>
・「街づくりについて」「子どもの居場所づくりについて」
「地域における子どもの活動について」・・・市の努力義務
<第四章 子どもの参加について>
・市の努力義務
・市長は川崎市子ども会議を開催する
<第五章 相談および救済>
・ 子どもは、川崎市人権オンブズパーソンに対し、権利の侵害について相談し、権利侵害からの救済を求めることができる。
・ 市は関係機関との連携に努める。
<第六章 子どもの権利に関する行動計画>
・市に行動計画策定の義務
<第七章 子どもの権利の保障状況の検証>
・権利委員会の設置(委員10名、任期3年)
<雑則、附則>
両輪を成す【人権オンブズパーソン条例】2001年6月~
===========================
 2:条例で何が変わるか
2:条例で何が変わるか
3:市民参加型条例のこれまでとこれから
4:動き始めた川崎
【動き】
1998年 条例制定検討委員会 設置
1999年
2000年 川崎市子どもの権利条例 制定
2001年 人権オンブズパーソン条例 制定
「市民サロン」1998年~2000年までに30回その後、月1回ペースで開催。
「子ども委員会」 1999年~2001年 第1期子ども委員会23回
第2期子ども委員会(30名)8回 ―その後、地区別子ども集会へ発展
「子ども会議準備委員会」 2001年~2002年 13回開催
「地域教育会議の実践」 ・・・10年以上前から、51の中学校区単位で子どもも参加し実施してきた。条例制定の際の取り組みとして住民、親等保護者、教育とともに、各地で子ども会議を開催。
<市民サロン(子どもの権利を考える市民サロン)>
・・・公募制。実態調査グループと、権利保障のあり方グループに分かれ活動。統一見解を作り、条例制定の調査研究委員会に提出した。
・・・条例制定の委員会を毎回傍聴→サロンで検討→傍聴→サロンで検討→。
・・・統一見解提出後は、7行政区単位での市民集会の開催に発展した。
<条例制定過程への、子どもの参加>
・・・もともとの基盤として
・ 1994年川崎市子ども議会(子どもが全市で意見表明)
・ 地域教育会議開催の中で、子ども会議発足
・ 1996年~「全市子ども人権集会」「全市子ども集会」
・・・権利条例制定の中で
・ 1999年~「子ども権利条例調査研究委員会」「子ども委員会」
「川崎市 子ども・夢・共和国」「アンケートの集約」
「外国籍の子どもとの交流会」「障害のある子どもたちとの交流会」
「全市子ども集会企画」
・ 地区別子ども集会・・・「土日土日が全部つぶれて大変ですが、やりがいがあります」(担当者談)
・ 「権利条例を策定する過程で、大人たちから『権利は子どもをわがままにする』という論調が多く出された時期がありました。でも、わたしが子ども委員会で得たものは、権利について話し合うことを通して、子どもはみずからのあり方をふりかえり、大きく生長するということです。家庭や学校のなかでも、子どもたちとともに、真剣に話し合う『場』と『時間』がとれることを願っています。」山田雅大(教育委員会 総務部 人権・共生教育担当)
<教育の動きの中での権利条例>
・ 1990年~地域教育会議(中学校区ごと)
・ 学校教育推進会議・・・すべての学校と幼稚園で実施していた(モデル校をつくらず)
・ より一層開かれた学校(園)づくりの推進を目的に、保護者、地域住民、幼児・児童・生徒、教職員、有識者等の意見を聴取する。
・ 子どもは「年齢や成熟にふさわしい参加のあり方を配慮」されてきた
<条例により始まった権利侵害救済制度>
・ 既存の市民オンブズマン活動に、条例により人権オンブズパーソン活動が加わった。
(女性、子どもの権利侵害救済の相談を受け付ける)
「個別救済活動+監視機能」
・ 子どもは、自分が困っていたり、悔しかったり、自分が感じている苦痛を他人に聞いて欲しいと思った段階で相談可。
・ オンブズパーソンの専門調査員が調査し、オンブズパーソンにより市への勧告や、意見表明を実施する。必要に応じて専門機関と連携する。
<第六章 行動計画の策定>
1)子どもの最善の利益に基づくものであること
2)教育、福祉、医療との連携および調整が図られた総合的なものであること(部局横断)
3)連携を通して一人ひとりの子どもを支援すること
===========================
(所感)
・ 市の条例を作ろうとの姿勢だけでなく、この動きの前から「子どもの参加と意見表明」「地域教育会議への子どもや住民の参加」という背景が川崎市にはあった。
・ 条例にかかわる市民サロンの開催(3年間で30回)、子ども委員会が3年で31回開かれ、子どもにより運営され、第一期、第二期として60人の子ども達が条例作りに主体的に関わった。この子たちが川崎市の子として成長していくということは地域にとってすごいこと。
・ 権利の保障は主に市、親等保護者、育ち学ぶ施設による努力義務となるが、子どもの実際の権利侵害救済制度として、「人権オンブズパーソン」を設置し、実際に救済に動ける仕組みを目指している。権利条例と救済申し立てはセットで必要か。
・ 大人だけで議論するのではなく、子ども自身による議論が不可欠(子どもサミット?)
 1:逐条解説
1:逐条解説【川崎市子どもの権利に関する条例】抜粋
<前文>
・ 「子ども観」「子どもの権利の理念」の考え方の違いを克服
・ 子どもを「保護される対象」から「自ら権利を行使する主体」へと転換
・ 子どもは権利について学習し、実際に行使することを通して権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任を身につける。
→権利の相互尊重によって「権利と責任(と義務)」の考え方を整理
<第一章 総則>
・子ども・・・18歳未満
<第三条 責任>
・ 市は子どもの権利を尊重し、その保障に努める。
・ 市民は、子どもの権利が保障されるよう市との協働に努めなければならない。
・ 育ち学ぶ施設の設置者、管理者、職員は市の施策に協力するよう努めるとともに、施設における子どもの権利が保障されるよう努めねばならない。
・ 事業者は、市の施策に協力するよう努めねばならない。
<第七条 学習等への支援等>
<第二章 人間として大切な子どもの権利>
・ 安心して生きる権利
・ ありのままの自分でいる権利
・ 自分を守り、守られる権利
・ 自分を豊かにし、力づけられる権利
・ 自分で決める権利
・ 参加する権利(意見表明の権利)
・ 個別の必要に応じて支援を受ける権利(差別の禁止)
<第三章 家庭・育ち学ぶ施設及び地域における子どもの権利の保障>
<第一節 親等による子どもの権利の保障>
・ 親は養育の支援を受けることができる
・ 親等・・・虐待及び体罰の禁止
・ 市の努力義務・・・虐待からの救済及びその回復
<第二節 育ち学ぶ施設における子どもの権利の保障>
・ 環境整備、安全管理体制整備の努力義務
・ 虐待及び体罰の禁止
・ 救済と回復の努力義務
・ いじめの防止の努力義務
<第三節 地域における子どもの権利の保障>
・「街づくりについて」「子どもの居場所づくりについて」
「地域における子どもの活動について」・・・市の努力義務
<第四章 子どもの参加について>
・市の努力義務
・市長は川崎市子ども会議を開催する
<第五章 相談および救済>
・ 子どもは、川崎市人権オンブズパーソンに対し、権利の侵害について相談し、権利侵害からの救済を求めることができる。
・ 市は関係機関との連携に努める。
<第六章 子どもの権利に関する行動計画>
・市に行動計画策定の義務
<第七章 子どもの権利の保障状況の検証>
・権利委員会の設置(委員10名、任期3年)
<雑則、附則>
両輪を成す【人権オンブズパーソン条例】2001年6月~
===========================
 2:条例で何が変わるか
2:条例で何が変わるか3:市民参加型条例のこれまでとこれから
4:動き始めた川崎
【動き】
1998年 条例制定検討委員会 設置
1999年
2000年 川崎市子どもの権利条例 制定
2001年 人権オンブズパーソン条例 制定
「市民サロン」1998年~2000年までに30回その後、月1回ペースで開催。
「子ども委員会」 1999年~2001年 第1期子ども委員会23回
第2期子ども委員会(30名)8回 ―その後、地区別子ども集会へ発展
「子ども会議準備委員会」 2001年~2002年 13回開催
「地域教育会議の実践」 ・・・10年以上前から、51の中学校区単位で子どもも参加し実施してきた。条例制定の際の取り組みとして住民、親等保護者、教育とともに、各地で子ども会議を開催。
<市民サロン(子どもの権利を考える市民サロン)>
・・・公募制。実態調査グループと、権利保障のあり方グループに分かれ活動。統一見解を作り、条例制定の調査研究委員会に提出した。
・・・条例制定の委員会を毎回傍聴→サロンで検討→傍聴→サロンで検討→。
・・・統一見解提出後は、7行政区単位での市民集会の開催に発展した。
<条例制定過程への、子どもの参加>
・・・もともとの基盤として
・ 1994年川崎市子ども議会(子どもが全市で意見表明)
・ 地域教育会議開催の中で、子ども会議発足
・ 1996年~「全市子ども人権集会」「全市子ども集会」
・・・権利条例制定の中で
・ 1999年~「子ども権利条例調査研究委員会」「子ども委員会」
「川崎市 子ども・夢・共和国」「アンケートの集約」
「外国籍の子どもとの交流会」「障害のある子どもたちとの交流会」
「全市子ども集会企画」
・ 地区別子ども集会・・・「土日土日が全部つぶれて大変ですが、やりがいがあります」(担当者談)
・ 「権利条例を策定する過程で、大人たちから『権利は子どもをわがままにする』という論調が多く出された時期がありました。でも、わたしが子ども委員会で得たものは、権利について話し合うことを通して、子どもはみずからのあり方をふりかえり、大きく生長するということです。家庭や学校のなかでも、子どもたちとともに、真剣に話し合う『場』と『時間』がとれることを願っています。」山田雅大(教育委員会 総務部 人権・共生教育担当)
<教育の動きの中での権利条例>
・ 1990年~地域教育会議(中学校区ごと)
・ 学校教育推進会議・・・すべての学校と幼稚園で実施していた(モデル校をつくらず)
・ より一層開かれた学校(園)づくりの推進を目的に、保護者、地域住民、幼児・児童・生徒、教職員、有識者等の意見を聴取する。
・ 子どもは「年齢や成熟にふさわしい参加のあり方を配慮」されてきた
<条例により始まった権利侵害救済制度>
・ 既存の市民オンブズマン活動に、条例により人権オンブズパーソン活動が加わった。
(女性、子どもの権利侵害救済の相談を受け付ける)
「個別救済活動+監視機能」
・ 子どもは、自分が困っていたり、悔しかったり、自分が感じている苦痛を他人に聞いて欲しいと思った段階で相談可。
・ オンブズパーソンの専門調査員が調査し、オンブズパーソンにより市への勧告や、意見表明を実施する。必要に応じて専門機関と連携する。
<第六章 行動計画の策定>
1)子どもの最善の利益に基づくものであること
2)教育、福祉、医療との連携および調整が図られた総合的なものであること(部局横断)
3)連携を通して一人ひとりの子どもを支援すること
===========================
(所感)
・ 市の条例を作ろうとの姿勢だけでなく、この動きの前から「子どもの参加と意見表明」「地域教育会議への子どもや住民の参加」という背景が川崎市にはあった。
・ 条例にかかわる市民サロンの開催(3年間で30回)、子ども委員会が3年で31回開かれ、子どもにより運営され、第一期、第二期として60人の子ども達が条例作りに主体的に関わった。この子たちが川崎市の子として成長していくということは地域にとってすごいこと。
・ 権利の保障は主に市、親等保護者、育ち学ぶ施設による努力義務となるが、子どもの実際の権利侵害救済制度として、「人権オンブズパーソン」を設置し、実際に救済に動ける仕組みを目指している。権利条例と救済申し立てはセットで必要か。
・ 大人だけで議論するのではなく、子ども自身による議論が不可欠(子どもサミット?)
子ども支援条例 公聴会&説明会開催決定!
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(全体像)
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)
子ども支援条例のパブリックコメント〆切まであと7日!
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)
長野県子ども支援条例骨子案 パブリックコメント募集中
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(全体像)
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)
子ども支援条例のパブリックコメント〆切まであと7日!
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)
長野県子ども支援条例骨子案 パブリックコメント募集中
Posted by usiki@しののい at 22:56│Comments(0)
│こども条例
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。