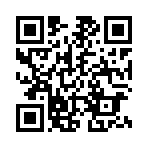2013年12月21日
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(全体像)
 長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切まで
長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切までハ_ハ あと3日!!! ハ_ハ
('(゚∀゚∩∧,,∧ ∧..∧ ∧..∧∩゚∀゚)')
O,_ 〈(´∀`)(´∀`)(´∀`) 〉 ,_O
`ヽ_)゚○-J゚ ゚○-J゚ ゚○-J゚ (_/´
「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について、ご意見を募集します
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/251125kossiikenbosyuu.html
長野県HPに、意見提出用紙(ワード形式、PDF形式)のファイルがあります。
<参考1>
「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」では、「中間とりまとめ」で示されたしくみづくりの基本的な方向性を踏まえるとともに、子ども部会等の意見を参考にしながら、具体的なしくみや条例に盛り込むべき事項等を検討してきましたが、その内容を「最終とりまとめ」としてまとめ、平成25年7月29日に知事に提出しました。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
<参考3 パブコメの論点について>
★骨子案全体について★
子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会の最終とりまとめの趣旨が全く生かされていません。2年半の間の委員会の活動が、特に子ども部会(SKIP)の提案を含めて生かされていないと思います。最終とりまとめの第4章第3節の「条例に盛り込むべき事項」を条例にしたものが必要だと思います。
★「子ども支援条例」という題名について★
しくみを考える委員会では、子どもには生きる意思と力があり、大人はこれが発揮できるように子どもを支えることが役割だという子ども観を前提に、「子ども支援」や「子どもの育ちを支える者への支援」を提言しました。しかし条例骨子案は、大人による一方的な(子どもの力を前提としない)子ども施策が記載されており、題名自体が大人目線の子ども施し条例というニュアンスになっています。「子ども条例」に名称を改め、前文や基本理念に子ども観を示すべきです。
★前文について★
① 前文は必要です。未来を担う子どもたちへの長野県としてのメッセージを出すことが必要です。他県では前文をつけていることが多く(三重県、高知県、滋賀県、秋田県、熊本県、京都府、大阪府、石川県他)、市町村ではほとんどに前文がついています。長野県の制定する条例に前例にないとのことですが(これ自体は確認できていませんが)、前文を入れない理由にはならないと思います。
② 前文は、最終とりまとめを生かして、「子どもは、一人の人間であり、そのいのちや尊厳や人格が大切にされ、社会の一員としてともに生きるパートナーである。子どもは生まれた時から生きる意思と力を持っている、子どもがその意思と力を発揮して能動的、自立的に活動しながら、のびのびと成長していくことができるように、おとなは支えていく。長野県はこの考えを実現するために、子どもの育ちにかかわるすべての関係者と連携し、協働して、子どもの育ちや子どもの育ちにかかわる人たちを支える仕組みを発展させ、子どもの最善の利益を実現するために、この条例を制定する。」としてはどうでしょうか。
★第1項「目的」について★
① この条例を策定する目的は、「すべての子どものいのちが大切にされ、尊厳と希望を持って日々を過ごし、社会を担う人間に成長できるように、子どもの育ちを支え、子どもの育ちにかかわる人たちを支援し、子どもの最善の利益を実現していくこと」として下さい。
② 骨子案は前半の技術的な記載と、後半の子どもの最善の利益とが結びついていないように思います。
★第3項「基本理念」について★
① 基本理念は最終とりまとめの第4章第3節「条例に盛り込むべき事項」3項「基本的な理念について」をそのまま盛り込んで下さい。 骨子案の主語が「子どもへの支援は」としてあるために、大人による施し条例になってしまっています。「子どもは・・・」とすべきです。
② (1)に「その人権が尊重されること」とあり、(3)に「相互に人権が尊重し合えるように」とあるが、これを記載するのであれば、その前提に、子どもには人権があることを明確に書くべきではないかと思います。それが子ども達へのメッセージであり、大人が子どもに接する基本を示すことになると思います。
③ (3)に「規範意識」という言葉が記載されていますが、この「規範」が問題で、大人の作った規範を子どもに押しつけるというのであれば、子どもは納得できません。規範は子どもが参加して作るべきであり、最終とりまとめの「自分の人権が尊重されるのと同じように、他の人の人権を尊重しながら、社会の一員として生きていけること」という記載で、子どもの規範意識の醸成は十分に実現可能だと思います。最終とりまとめを生かして下さい。
④ (4)(5)は、基本理念にはふさわしくないと思います。(5)を骨子案のどこかにいれるのであれば、「地域」を入れて下さい。最終とりまとめは、条例にする必要性として、子ども施策の継続性、総合性、重畳性の確保をあげていますが(53頁)、これはきわめて大事な提言であり、(5)の後半は、「・・・各々の役割を果たしながら、総合的、重畳的に行うとともに、相互に連携及び協力して継続的に行わなければならない。」としたらどうでしょうか。
★第5項「基本的施策」★
(1)「主に子どもへの支援」について
①「子どもに対する相談体制の充実」について
表題は「子どもに対する総合的な相談及び救済機関の設置」とし、以下を盛り込んで下さい。
骨子案は、現在の長野県の相談体制を前提に、これを子どもが安心して相談できるような態勢にし、その相談体制を県民に案内することが内容のようです。しかし現在の教育委員会の子ども支援センターの相談体制ではもはや子どもは救えません。委員会のアンケートでもチャイルドライン以外の相談機関の子どもへの認知率は高くありませんでした。多様な相談に対応できるワンストップの窓口であること、相談担当者は、傾聴・受容に努め、伴走者として子どものエンパワメントを促すことができる者であること、我慢してしまい容易にSOSを出せない子どもが相談する気持ちになれる体制であること等々が必要です(最終報告45頁以下)。そのために相談員の専門性の確保や救済機関と一体であることが必要で、総合的な相談・救済機関を知事部局に設置することが必要です。このことを明記して下さい。
② 「子どもの社会参加の促進」について
この記載では、社会参加がなぜ必要かがわかりません。「子どもの参加が、自己肯定感の向上、成長発達、社会的自立に欠かせない営みであることをふまえ、県は、・・・・」として下さい。単に「・・・・体験の機会の提供」だけでなく、子どもの社会参加の具体的内容を記載して下さい。
③ 「子どもの居場所」について
子どもの居場所の必要性がわかりません。「地域における子どもの居場所が、子どもにとって安心できる場であるとともに、遊び、学び、活動し、人間関係を築いていくことができる大切な場であることをふまえ、県は・・・」として下さい。居場所として地域やNPOを入れて下さい。子どもにとって大変重要な場となります。場所の確保という物的施設の点しか記載されていませんが、プレーリーダー、ファシリテーター、サポーター等の養成その他人的設備の充実を入れて下さい。県はそのための補助金支出などの支援方法は可能です。
④ 「人権教育」について
三重県のように、「子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提供する」等と明瞭に記載したらどうでしょうか。
(2)「主に子どもを支える者への支援」について
①「学校等関係者に対する支援」について
「学校等関係者に対する支援」の(2)は、どういう必要があって、具体的に何をするのかが分りません。この条例は教職員も支援するものである以上、現在の教職員の置かれている現状を直視し、県がすべきことを明記すべきです。最終とりまとめにあるとおり、「県は、教職員がいっそう職務に専念できるように、直接かつ容易に相談でき、第三者的立場からの助言や支援が受けられるしくみの導入その他の適切な措置により、教職員を総合的に支援する。教職員がいっそう児童生徒と向き合えるように、・・・教育環境の整備その他の条件を整備する。」として下さい。
②「関係者による連携及び協力」について
「子どもの育ちを支える者を支援するため」の前に「子ども及び」を入れるべきです。その後の「関係機関」、「関係団体」が具体的にどの組織をさすのかわかりません。地域、民間、ネットワークが共同する、等と明確に書くべきです(児童福祉法25条の2を参考にしたらどうか)。ただし その場合、守秘義務を民間団体にも課す必要があります。
「関係者による連携及び協力」の(2)は、連携・協力の意義がわかりにくい。最終報告書の地域支援ネットワークを意識して、「家庭、子ども施設、地域、民間団体などが有機的につながり、情報を適切に共有し、相互に連携、協働がはかられるよう、県は、コーディネーターの配置その他、必要な措置を講ずるものとする。」としたらどうでしょうか。
★第6項「相談・救済」★
(1)「子どもの相談に応じる総合的な窓口」は、上述のとおりです。
(2)「子ども支援委員会」について
① 骨子案は、相談機関と救済機関を別にし、子ども支援委員会は、救済申出を受けてその申出を審議する機関とされています。しかし相談と救済は一体とし、子ども支援委員のもとで相談し、その中で救済に必要な案件を救済していく態勢が必要で、オンブズパーソンの権限を持った機関を作るべきであって、最終とりまとめのとおりでよいと思います。
② 子ども支援委員会は、救済申出の審議機関とされ、審議し、関係機関に意見・勧告するのがその任務とされていますが、これでは現実の子どもは救済できません。関係機関(特に学校)としては、このような制度の受け容れには抵抗があるのではないでしょうか。 いじめ、体罰、セクハラ、虐待等子どもの人権救済機能で重要なのは、人権侵害の現状を知り、その原因を探り、関係者間を調整して原因を解消することです。救済機関の主な役割はこの調整機能であるのに、この機能が含まれていないのでは迅速、適切な解決ははかれません。子ども支援委員(会)には、修復的対話の機能を持たせるべきです。
③ 委員を3人以内とした趣旨が理解できません。長野県は広く、県内の人権侵害事件に対応するためには、各地域からの推薦者も4人程度は入れる必要があり、7人以上として下さい。将来は各基礎自治体に子どもの人権救済機関ができることが理想ですが、当面は県に作って全県的に対応するしかありません。
また、基礎自治体に置かれても、二重に県にも設置することが必要です。そのためにも県の救済機関は調整機能を持たせることと、委員の人数も相当数が必要です。
④ 骨子案は子ども支援委員会として、委員の合議制をとっていますが、調整機能を持たせるならば、「支援委員」制度として、委員個人が個別の救済事案にあたることができるようにすべきです。
★第7項「条例に基づく施策の推進」★
(2)「施策の実施状況等の公表」について
条例に基づいた子どもの施策が行われるよう、チェックすることが必要です。そのために子ども施策を毎年検証し、その結果を次の行動計画に反映させて下さい。この場合行動計画の策定の際は、多くの外国で行われているとおり、子どもの意見を聞き、これを実現する内容にすることが必要です。
★最後に★
骨子案には、最終とりまとめ「条例に盛り込むべき事項」第2第4項に記載された「特に困難を状況下の子どもへの支援」が記載されていません。これはすでに施策が行われているとか、担当部署がちがうとの趣旨で落とされたのかもしれませんが、現在の施策は、なされていないか施策が不十分です。不登校の子、発達障害のある子、非行少年、居場所を失った子、経済的な困難を抱える子、その他生きずらさを感じている子に対する支援は特に必要であり、今必要なのは子どもに関する総合条例ですので、これらの子どもへの支援も当然に条例に盛り込むできです。
子ども支援条例 公聴会&説明会開催決定!
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)
子ども支援条例のパブリックコメント〆切まであと7日!
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)
長野県子ども支援条例骨子案 パブリックコメント募集中
~長野県の「子ども条例」制定に向けて~」
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)
子ども支援条例のパブリックコメント〆切まであと7日!
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)
長野県子ども支援条例骨子案 パブリックコメント募集中
~長野県の「子ども条例」制定に向けて~」
Posted by usiki@しののい at 23:50│Comments(0)
│こども条例
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。