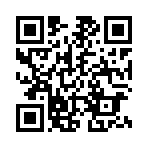子ども支援条例 公聴会&説明会開催決定!
新年あけましておめでとうございます。
今年はいよいよ条例制定の年、長野県の子ども条例が実りあるものになることを願っています。
Children first
Children friendly な社会づくりが地域の未来を創ることにつながります。
さて、長野県子ども支援条例(仮称)骨子案へのパブリックコメントが12月24日で受付終了となりました。
なんと、500件を超えるパブコメが寄せられたとのことで、賛否両論集まったようです。
議論していくことが子育て・子育ちを支えることにつながっていくと思います。みなさまに感謝感謝です。
こういう議論を、子どもや若者との意見交換を入れながらやれるともっと素敵だと思うのですが。。。
11月県議会でも、もっと県民にこの子ども条例づくりのことを知らせて、県民議論を深める必要があるとの議会質問が出されたため、
公聴会&説明会が開催される流れになりました。
(^^)ノ 行政説明だけで終わらず、意見交換もありとのことで、直接県の担当者や委員会の委員さんと話し合えるまたとない機会です。
今年はいよいよ条例制定の年、長野県の子ども条例が実りあるものになることを願っています。
Children first
Children friendly な社会づくりが地域の未来を創ることにつながります。
さて、長野県子ども支援条例(仮称)骨子案へのパブリックコメントが12月24日で受付終了となりました。
なんと、500件を超えるパブコメが寄せられたとのことで、賛否両論集まったようです。
議論していくことが子育て・子育ちを支えることにつながっていくと思います。みなさまに感謝感謝です。
こういう議論を、子どもや若者との意見交換を入れながらやれるともっと素敵だと思うのですが。。。
11月県議会でも、もっと県民にこの子ども条例づくりのことを知らせて、県民議論を深める必要があるとの議会質問が出されたため、
公聴会&説明会が開催される流れになりました。
(^^)ノ 行政説明だけで終わらず、意見交換もありとのことで、直接県の担当者や委員会の委員さんと話し合えるまたとない機会です。
ぜひ、お誘いあわせて参加されてくださいm(_ _)m
1月10日(金)の方は県の委員会の委員長で、早稲田大学教授の喜多明人先生(「子ども支援とまちづくり」が研究活動のテーマ。日本教育法学会理事。子どもの権利条約ネットワーク(NCRC)代表)も参加するとのことです。
1月8日(水)は委員会副委員長の北川和彦先生(弁護士)が参加されます。
[長野県ホームページ参照]
https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/ikentyousyukai.html
松本会場 平成26年1月8日(水)午後6時から7時30分
県松本合同庁舎 講堂(松本市大字島立1020)
※松本IC降りて車5分ほど。松本駅からは巡廻バス乗車。
長野会場 平成26年1月10日(金)午後3時から4時30分
長野保健福祉事務所 3階会議室(長野市中御所岡田98-1)
※県庁の南向かい側徒歩すぐの建物です。
1月10日(金)の方は県の委員会の委員長で、早稲田大学教授の喜多明人先生(「子ども支援とまちづくり」が研究活動のテーマ。日本教育法学会理事。子どもの権利条約ネットワーク(NCRC)代表)も参加するとのことです。
1月8日(水)は委員会副委員長の北川和彦先生(弁護士)が参加されます。
[長野県ホームページ参照]
https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/ikentyousyukai.html
松本会場 平成26年1月8日(水)午後6時から7時30分
県松本合同庁舎 講堂(松本市大字島立1020)
※松本IC降りて車5分ほど。松本駅からは巡廻バス乗車。
長野会場 平成26年1月10日(金)午後3時から4時30分
長野保健福祉事務所 3階会議室(長野市中御所岡田98-1)
※県庁の南向かい側徒歩すぐの建物です。

詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(全体像)
 長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切まで
長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切までハ_ハ あと3日!!! ハ_ハ
('(゚∀゚∩∧,,∧ ∧..∧ ∧..∧∩゚∀゚)')
O,_ 〈(´∀`)(´∀`)(´∀`) 〉 ,_O
`ヽ_)゚○-J゚ ゚○-J゚ ゚○-J゚ (_/´
「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について、ご意見を募集します
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/251125kossiikenbosyuu.html
長野県HPに、意見提出用紙(ワード形式、PDF形式)のファイルがあります。
<参考1>
「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」では、「中間とりまとめ」で示されたしくみづくりの基本的な方向性を踏まえるとともに、子ども部会等の意見を参考にしながら、具体的なしくみや条例に盛り込むべき事項等を検討してきましたが、その内容を「最終とりまとめ」としてまとめ、平成25年7月29日に知事に提出しました。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
<参考3 パブコメの論点について>
★骨子案全体について★
子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会の最終とりまとめの趣旨が全く生かされていません。2年半の間の委員会の活動が、特に子ども部会(SKIP)の提案を含めて生かされていないと思います。最終とりまとめの第4章第3節の「条例に盛り込むべき事項」を条例にしたものが必要だと思います。
★「子ども支援条例」という題名について★
しくみを考える委員会では、子どもには生きる意思と力があり、大人はこれが発揮できるように子どもを支えることが役割だという子ども観を前提に、「子ども支援」や「子どもの育ちを支える者への支援」を提言しました。しかし条例骨子案は、大人による一方的な(子どもの力を前提としない)子ども施策が記載されており、題名自体が大人目線の子ども施し条例というニュアンスになっています。「子ども条例」に名称を改め、前文や基本理念に子ども観を示すべきです。
★前文について★
① 前文は必要です。未来を担う子どもたちへの長野県としてのメッセージを出すことが必要です。他県では前文をつけていることが多く(三重県、高知県、滋賀県、秋田県、熊本県、京都府、大阪府、石川県他)、市町村ではほとんどに前文がついています。長野県の制定する条例に前例にないとのことですが(これ自体は確認できていませんが)、前文を入れない理由にはならないと思います。
② 前文は、最終とりまとめを生かして、「子どもは、一人の人間であり、そのいのちや尊厳や人格が大切にされ、社会の一員としてともに生きるパートナーである。子どもは生まれた時から生きる意思と力を持っている、子どもがその意思と力を発揮して能動的、自立的に活動しながら、のびのびと成長していくことができるように、おとなは支えていく。長野県はこの考えを実現するために、子どもの育ちにかかわるすべての関係者と連携し、協働して、子どもの育ちや子どもの育ちにかかわる人たちを支える仕組みを発展させ、子どもの最善の利益を実現するために、この条例を制定する。」としてはどうでしょうか。
★第1項「目的」について★
① この条例を策定する目的は、「すべての子どものいのちが大切にされ、尊厳と希望を持って日々を過ごし、社会を担う人間に成長できるように、子どもの育ちを支え、子どもの育ちにかかわる人たちを支援し、子どもの最善の利益を実現していくこと」として下さい。
② 骨子案は前半の技術的な記載と、後半の子どもの最善の利益とが結びついていないように思います。
★第3項「基本理念」について★
① 基本理念は最終とりまとめの第4章第3節「条例に盛り込むべき事項」3項「基本的な理念について」をそのまま盛り込んで下さい。 骨子案の主語が「子どもへの支援は」としてあるために、大人による施し条例になってしまっています。「子どもは・・・」とすべきです。
② (1)に「その人権が尊重されること」とあり、(3)に「相互に人権が尊重し合えるように」とあるが、これを記載するのであれば、その前提に、子どもには人権があることを明確に書くべきではないかと思います。それが子ども達へのメッセージであり、大人が子どもに接する基本を示すことになると思います。
③ (3)に「規範意識」という言葉が記載されていますが、この「規範」が問題で、大人の作った規範を子どもに押しつけるというのであれば、子どもは納得できません。規範は子どもが参加して作るべきであり、最終とりまとめの「自分の人権が尊重されるのと同じように、他の人の人権を尊重しながら、社会の一員として生きていけること」という記載で、子どもの規範意識の醸成は十分に実現可能だと思います。最終とりまとめを生かして下さい。
④ (4)(5)は、基本理念にはふさわしくないと思います。(5)を骨子案のどこかにいれるのであれば、「地域」を入れて下さい。最終とりまとめは、条例にする必要性として、子ども施策の継続性、総合性、重畳性の確保をあげていますが(53頁)、これはきわめて大事な提言であり、(5)の後半は、「・・・各々の役割を果たしながら、総合的、重畳的に行うとともに、相互に連携及び協力して継続的に行わなければならない。」としたらどうでしょうか。
★第5項「基本的施策」★
(1)「主に子どもへの支援」について
①「子どもに対する相談体制の充実」について
表題は「子どもに対する総合的な相談及び救済機関の設置」とし、以下を盛り込んで下さい。
骨子案は、現在の長野県の相談体制を前提に、これを子どもが安心して相談できるような態勢にし、その相談体制を県民に案内することが内容のようです。しかし現在の教育委員会の子ども支援センターの相談体制ではもはや子どもは救えません。委員会のアンケートでもチャイルドライン以外の相談機関の子どもへの認知率は高くありませんでした。多様な相談に対応できるワンストップの窓口であること、相談担当者は、傾聴・受容に努め、伴走者として子どものエンパワメントを促すことができる者であること、我慢してしまい容易にSOSを出せない子どもが相談する気持ちになれる体制であること等々が必要です(最終報告45頁以下)。そのために相談員の専門性の確保や救済機関と一体であることが必要で、総合的な相談・救済機関を知事部局に設置することが必要です。このことを明記して下さい。
② 「子どもの社会参加の促進」について
この記載では、社会参加がなぜ必要かがわかりません。「子どもの参加が、自己肯定感の向上、成長発達、社会的自立に欠かせない営みであることをふまえ、県は、・・・・」として下さい。単に「・・・・体験の機会の提供」だけでなく、子どもの社会参加の具体的内容を記載して下さい。
③ 「子どもの居場所」について
子どもの居場所の必要性がわかりません。「地域における子どもの居場所が、子どもにとって安心できる場であるとともに、遊び、学び、活動し、人間関係を築いていくことができる大切な場であることをふまえ、県は・・・」として下さい。居場所として地域やNPOを入れて下さい。子どもにとって大変重要な場となります。場所の確保という物的施設の点しか記載されていませんが、プレーリーダー、ファシリテーター、サポーター等の養成その他人的設備の充実を入れて下さい。県はそのための補助金支出などの支援方法は可能です。
④ 「人権教育」について
三重県のように、「子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提供する」等と明瞭に記載したらどうでしょうか。
(2)「主に子どもを支える者への支援」について
①「学校等関係者に対する支援」について
「学校等関係者に対する支援」の(2)は、どういう必要があって、具体的に何をするのかが分りません。この条例は教職員も支援するものである以上、現在の教職員の置かれている現状を直視し、県がすべきことを明記すべきです。最終とりまとめにあるとおり、「県は、教職員がいっそう職務に専念できるように、直接かつ容易に相談でき、第三者的立場からの助言や支援が受けられるしくみの導入その他の適切な措置により、教職員を総合的に支援する。教職員がいっそう児童生徒と向き合えるように、・・・教育環境の整備その他の条件を整備する。」として下さい。
②「関係者による連携及び協力」について
「子どもの育ちを支える者を支援するため」の前に「子ども及び」を入れるべきです。その後の「関係機関」、「関係団体」が具体的にどの組織をさすのかわかりません。地域、民間、ネットワークが共同する、等と明確に書くべきです(児童福祉法25条の2を参考にしたらどうか)。ただし その場合、守秘義務を民間団体にも課す必要があります。
「関係者による連携及び協力」の(2)は、連携・協力の意義がわかりにくい。最終報告書の地域支援ネットワークを意識して、「家庭、子ども施設、地域、民間団体などが有機的につながり、情報を適切に共有し、相互に連携、協働がはかられるよう、県は、コーディネーターの配置その他、必要な措置を講ずるものとする。」としたらどうでしょうか。
★第6項「相談・救済」★
(1)「子どもの相談に応じる総合的な窓口」は、上述のとおりです。
(2)「子ども支援委員会」について
① 骨子案は、相談機関と救済機関を別にし、子ども支援委員会は、救済申出を受けてその申出を審議する機関とされています。しかし相談と救済は一体とし、子ども支援委員のもとで相談し、その中で救済に必要な案件を救済していく態勢が必要で、オンブズパーソンの権限を持った機関を作るべきであって、最終とりまとめのとおりでよいと思います。
② 子ども支援委員会は、救済申出の審議機関とされ、審議し、関係機関に意見・勧告するのがその任務とされていますが、これでは現実の子どもは救済できません。関係機関(特に学校)としては、このような制度の受け容れには抵抗があるのではないでしょうか。 いじめ、体罰、セクハラ、虐待等子どもの人権救済機能で重要なのは、人権侵害の現状を知り、その原因を探り、関係者間を調整して原因を解消することです。救済機関の主な役割はこの調整機能であるのに、この機能が含まれていないのでは迅速、適切な解決ははかれません。子ども支援委員(会)には、修復的対話の機能を持たせるべきです。
③ 委員を3人以内とした趣旨が理解できません。長野県は広く、県内の人権侵害事件に対応するためには、各地域からの推薦者も4人程度は入れる必要があり、7人以上として下さい。将来は各基礎自治体に子どもの人権救済機関ができることが理想ですが、当面は県に作って全県的に対応するしかありません。
また、基礎自治体に置かれても、二重に県にも設置することが必要です。そのためにも県の救済機関は調整機能を持たせることと、委員の人数も相当数が必要です。
④ 骨子案は子ども支援委員会として、委員の合議制をとっていますが、調整機能を持たせるならば、「支援委員」制度として、委員個人が個別の救済事案にあたることができるようにすべきです。
★第7項「条例に基づく施策の推進」★
(2)「施策の実施状況等の公表」について
条例に基づいた子どもの施策が行われるよう、チェックすることが必要です。そのために子ども施策を毎年検証し、その結果を次の行動計画に反映させて下さい。この場合行動計画の策定の際は、多くの外国で行われているとおり、子どもの意見を聞き、これを実現する内容にすることが必要です。
★最後に★
骨子案には、最終とりまとめ「条例に盛り込むべき事項」第2第4項に記載された「特に困難を状況下の子どもへの支援」が記載されていません。これはすでに施策が行われているとか、担当部署がちがうとの趣旨で落とされたのかもしれませんが、現在の施策は、なされていないか施策が不十分です。不登校の子、発達障害のある子、非行少年、居場所を失った子、経済的な困難を抱える子、その他生きずらさを感じている子に対する支援は特に必要であり、今必要なのは子どもに関する総合条例ですので、これらの子どもへの支援も当然に条例に盛り込むできです。
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)
長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切まで
ハ_ハ あと5日!!! ハ_ハ
('(゚∀゚∩∧,,∧ ∧..∧ ∧..∧∩゚∀゚)')
O,_ 〈(´∀`)(´∀`)(´∀`) 〉 ,_O
`ヽ_)゚○-J゚ ゚○-J゚ ゚○-J゚ (_/´

パブリックコメントのポイント
ハ_ハ あと5日!!! ハ_ハ
('(゚∀゚∩∧,,∧ ∧..∧ ∧..∧∩゚∀゚)')
O,_ 〈(´∀`)(´∀`)(´∀`) 〉 ,_O
`ヽ_)゚○-J゚ ゚○-J゚ ゚○-J゚ (_/´

パブリックコメントのポイント
【骨子案修正のポイント】
★三重県子ども条例のように、毎年県の施策の実施状況を評価し、年次報告としてとりまとめ、公表するとともに、施策への反映に努める。とする行政の義務規定を(施策への反映に努めるの部分、重要)盛り込む。
★三重県では、条例に基づく調査の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、子どもをとりまく大人の意識や社会の状況などを「みえの子ども白書」として定期的にまとめている。
白書の内容は、子ども、保護者や学校関係者、企業、地域のさまざまな団体、市町・県といった行政などで広く共有し、子どもと大人が理解しあったり、地域で連携して子どもの育ちを支えるための取り組みにつなげられている。
★川崎市のように「行動計画を策定するに当たっては,市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。」と義務づける
(1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
(2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
(3)親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。(川崎市版)
★現骨子案の【知事は、毎年、県が講じた子ども支援に関する施策の実施状況等の概要を公表しなければならない】だけでは、単なる行政の任意の実績報告の公表になる恐れが大きい。事業評価、改善のPDCAサイクルに取り組むことが難しくなる。
★長野県骨子では、子ども支援の推進計画の策定をうたっていない。子ども・子育て関連3法(http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomo3houan/)を根拠として長野県子ども・子育て会議を来年度新たに設置し、推進計画を別途策定する方向であるようだが、松本市子どもの権利に関する条例の「子どもにやさしいまちづくり委員会」、射水市子ども条例の「射水市子ども施策推進委員会」、高知県子ども条例の「高知県子どもの環境づくり推進委員会」等のように、子ども条例の中に計画策定、計画推進、施策評価を条例に盛り込むことが大切。条例は条例、計画は計画とタテワリ行政で施策が整合性なく増えていかないために。
★石川県では、いしかわ子ども総合条例として子どもに関わる施策全てを網羅した総合条例になっている。そういう県もある。
【長野県子ども支援条例骨子案を見てみよう~不明確な施策の推進体制、事業評価フィードバックの定義なし~】
■4 子ども支援に関係する者の役割
(1)県は、基本理念にのっとり、地域における県民の主体的で自主的な子ども支援のための取組を尊重し、子ども支援施策を推進します。
子ども支援施策を推進するに当たっては、市町村等と連携を図ります。
( 2)子ども支援施策を推進するに当たっては、子どもが意見を出すことが容易になるよう配慮しながら、その意見を聴くよう努めます。
■7 条例に基づく施策の推進
(1)広報活動の充実
県は、基本理念に関する県民の理解を深めるため、子ども支援に関する広報活動の充実その他の措置を講ずるものとします。
(2)施策の実施状況等の公表
知事は、毎年、県が講じた子ども支援に関する施策の実施状況等の概要を公表しなければならないものとします。
【他自治体の条例概観】
「松本市子どもの権利に関する条例」
[子どもに優しいまちづくり委員会が推進計画の進行状況を公表]
(推進計画)
第22条 市は、施策を推進するにあたり、子どもの状況を把握し、現状認識を共通にし、市などが連携し、協働できるよう子どもに関する資料をまとめ、検証するとともに、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを総合的に、そして継続的に推進するため、子どもの権利に関する推進計画(以下「推進計画」といいます。)をつくります。
2 市は、推進計画をつくるときには、子どもをはじめ市民や、第23条に定める松本市子どもにやさしいまちづくり委員会の意見を聴きます。
3 市は、推進計画及びその進行状況について、広く市民に公表します。
(子どもにやさしいまちづくり委員会)
第23条 2 委員会の委員は、15人以内とします。
3 委員は、人権、健康、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。
(委員会の職務)
(提言やその尊重)
第25条 委員会は、調査や審議の結果を市長その他執行機関に報告し、提言します。
2 市長その他執行機関は、委員会からの報告や提言を尊重し、必要な措置をとります。
「川崎市子どもの権利に関する条例」
[子どもの権利に関する行動計画の策定を規定。策定及び推進状況は委員会の評価を受ける]
■第6章 子どもの権利に関する行動計画
(行動計画)
第36条 市は,子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に図られるための川崎市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 市長その他の執行機関は,行動計画を策定するに当たっては,市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。
(子どもに関する施策の推進)
第37条 市の子どもに関する施策は,子どもの権利の保障に資するため,次に掲げる事項に配慮し,推進しなければならない。
(1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
(2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
(3)親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。
(検証)
第39条 権利委員会は,前条第2項の諮問があったときは,市長その他の執行機関に対し,その諮問に係る施策について評価等を行うべき事項について提示するものとする。
2 市長その他の執行機関は,前項の規定により権利委員会から提示のあった事項について評価等を行い,その結果を権利委員会に報告するものとする。
3 権利委員会は,前項の報告を受けたときは,市民の意見を求めるものとする。
4 権利委員会は,前項の規定により意見を求めるに当たっては,子どもの意見が得られるようその方法等に配慮しなければならない。
5 権利委員会は,第2項の報告及び第3項の意見を総合的に勘案して,子どもの権利の保障の状況について調査審議するものとする。
6 権利委員会は,前項の調査審議により得た検証の結果を市長その他の執行機関に答申するものとする。
(答申に対する措置等)
第40条 市長その他の執行機関は,権利委員会からの答申を尊重し,必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は,前条の規定による答申及び前項の規定により講じた措置について公表するものとする。
「射水氏こども条例」
[射水市子どもに関する施策推進委員会が設置され、推進計画を策定]
■(推進計画)
第10条 市は、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、射水市子どもに関する施策推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画を策定するに当たっては、第11条第1項に規定する射水市子ども施策推進委員会の意見を聴くとともに、広く市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。
[射水市少子化対策及び子ども施策に関する推進計画にかかるアンケート調査]毎年実施
■(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。
「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」
[オンブズパーソンより毎年報告書が公表される]
■(運営状況等の報告及び公表)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況等について、市長に文書で報告するとともに、これを公表するものとする。
(子ども及び市民への広報等)
第21条 市の機関は、子ども及び市民にこの条例の趣旨及び内容を広く知らせるとともに、子どもがオンブズパーソンへの相談並びに擁護及び救済の申立てを容易に行うことができるため必要な施策の推進に努めるものとする。
「秋田県子ども・子育て支援条例」
[子ども・子育て支援について基本的な計画を本条例に基づき定めるとしている]
■第二章 基本的施策
(基本計画)
第八条 知事は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子ども・子育て支援に関する目標及び施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための重要事項
「高知県子ども条例」
[高知県子どもの環境づくり推進委員会の設置により推進計画の策定を義務付けている]
■第10条 県は、この条例の目的及び基本理念を実現するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき指針
(2) 前号に掲げるもののほか、子どもの環境づくりに関する取組を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
高知県子ども条例[施策推進委員会の定義あり]
■(推進委員会の設置等)
第11条 子どもの環境づくりに関する施策を推進するため、高知県子どもの環境づくり推進委員会(以下この条において「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 推進計画の作成及び変更に関すること並びにこの条例の目的の実現に関する重要な事項を調査審議すること。
(2) 推進計画に基づき県が実施する子どもの環境づくりに関する取組の状況について、知事に対して意見を述べること。
(広報及び啓発)
第12条 県は、この条例の目的及び基本理念についての理解が促進されるよう、広報及び啓発に努めるものとする。
「三重県子ども条例」
[推進計画の策定義務には言及していないが、施策の基本事項を定めた]
[また、施策実施状況を毎年評価し、年次報告書「みえの子ども白書」を発行]
■(施策の基本となる事項)
第11 条 県は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項の確保を旨とするものとする。
(1)子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提供すること。
(2)子どもに係る施策に関して、子どもが意見を表明する機会を設け、参加を促すとともに、子どもの意見を尊重すること。
(3)子どもが、自らの力を発揮して育つことができるよう、主体的に取り組む様々な活動を支援すること。
(4)子どもの育ちを見守り、及び支えるための人材の育成を行うとともに、保護者、学校関係者等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町が行う活動の促進が図られるよう、環境の整備を行うこと。
(広報及び啓発)
第13 条 県は、子どもの育ちについての県民の関心及び理解を深めるとともに、県民が行う子どもの育ちを見守り、及び支える活動を促進するため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
■(年次報告)
第15 条 知事は、毎年、この条例に基づき県が行う施策の実施状況を評価し、これを年次報告として取りまとめ、公表するとともに、施策への反映に努めるものとする。
条例に基づく調査の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、子どもをとりまく大人の意識や社会の状況などを「みえの子ども白書」として定期的にまとめます。
白書の内容は、子ども、保護者や学校関係者、企業、地域のさまざまな団体、市町・県といった行政などで広く共有し、子どもと大人が理解しあったり、地域で連携して子どもの育ちを支えるための取り組みにつなげたりします。

★三重県では、条例に基づく調査の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、子どもをとりまく大人の意識や社会の状況などを「みえの子ども白書」として定期的にまとめている。
白書の内容は、子ども、保護者や学校関係者、企業、地域のさまざまな団体、市町・県といった行政などで広く共有し、子どもと大人が理解しあったり、地域で連携して子どもの育ちを支えるための取り組みにつなげられている。
★川崎市のように「行動計画を策定するに当たっては,市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。」と義務づける
(1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
(2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
(3)親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。(川崎市版)
★現骨子案の【知事は、毎年、県が講じた子ども支援に関する施策の実施状況等の概要を公表しなければならない】だけでは、単なる行政の任意の実績報告の公表になる恐れが大きい。事業評価、改善のPDCAサイクルに取り組むことが難しくなる。
★長野県骨子では、子ども支援の推進計画の策定をうたっていない。子ども・子育て関連3法(http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomo3houan/)を根拠として長野県子ども・子育て会議を来年度新たに設置し、推進計画を別途策定する方向であるようだが、松本市子どもの権利に関する条例の「子どもにやさしいまちづくり委員会」、射水市子ども条例の「射水市子ども施策推進委員会」、高知県子ども条例の「高知県子どもの環境づくり推進委員会」等のように、子ども条例の中に計画策定、計画推進、施策評価を条例に盛り込むことが大切。条例は条例、計画は計画とタテワリ行政で施策が整合性なく増えていかないために。
★石川県では、いしかわ子ども総合条例として子どもに関わる施策全てを網羅した総合条例になっている。そういう県もある。
【長野県子ども支援条例骨子案を見てみよう~不明確な施策の推進体制、事業評価フィードバックの定義なし~】
■4 子ども支援に関係する者の役割
(1)県は、基本理念にのっとり、地域における県民の主体的で自主的な子ども支援のための取組を尊重し、子ども支援施策を推進します。
子ども支援施策を推進するに当たっては、市町村等と連携を図ります。
( 2)子ども支援施策を推進するに当たっては、子どもが意見を出すことが容易になるよう配慮しながら、その意見を聴くよう努めます。
■7 条例に基づく施策の推進
(1)広報活動の充実
県は、基本理念に関する県民の理解を深めるため、子ども支援に関する広報活動の充実その他の措置を講ずるものとします。
(2)施策の実施状況等の公表
知事は、毎年、県が講じた子ども支援に関する施策の実施状況等の概要を公表しなければならないものとします。
【他自治体の条例概観】
「松本市子どもの権利に関する条例」
[子どもに優しいまちづくり委員会が推進計画の進行状況を公表]
(推進計画)
第22条 市は、施策を推進するにあたり、子どもの状況を把握し、現状認識を共通にし、市などが連携し、協働できるよう子どもに関する資料をまとめ、検証するとともに、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを総合的に、そして継続的に推進するため、子どもの権利に関する推進計画(以下「推進計画」といいます。)をつくります。
2 市は、推進計画をつくるときには、子どもをはじめ市民や、第23条に定める松本市子どもにやさしいまちづくり委員会の意見を聴きます。
3 市は、推進計画及びその進行状況について、広く市民に公表します。
(子どもにやさしいまちづくり委員会)
第23条 2 委員会の委員は、15人以内とします。
3 委員は、人権、健康、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。
(委員会の職務)
(提言やその尊重)
第25条 委員会は、調査や審議の結果を市長その他執行機関に報告し、提言します。
2 市長その他執行機関は、委員会からの報告や提言を尊重し、必要な措置をとります。
「川崎市子どもの権利に関する条例」
[子どもの権利に関する行動計画の策定を規定。策定及び推進状況は委員会の評価を受ける]
■第6章 子どもの権利に関する行動計画
(行動計画)
第36条 市は,子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に図られるための川崎市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 市長その他の執行機関は,行動計画を策定するに当たっては,市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。
(子どもに関する施策の推進)
第37条 市の子どもに関する施策は,子どもの権利の保障に資するため,次に掲げる事項に配慮し,推進しなければならない。
(1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
(2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
(3)親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。
(検証)
第39条 権利委員会は,前条第2項の諮問があったときは,市長その他の執行機関に対し,その諮問に係る施策について評価等を行うべき事項について提示するものとする。
2 市長その他の執行機関は,前項の規定により権利委員会から提示のあった事項について評価等を行い,その結果を権利委員会に報告するものとする。
3 権利委員会は,前項の報告を受けたときは,市民の意見を求めるものとする。
4 権利委員会は,前項の規定により意見を求めるに当たっては,子どもの意見が得られるようその方法等に配慮しなければならない。
5 権利委員会は,第2項の報告及び第3項の意見を総合的に勘案して,子どもの権利の保障の状況について調査審議するものとする。
6 権利委員会は,前項の調査審議により得た検証の結果を市長その他の執行機関に答申するものとする。
(答申に対する措置等)
第40条 市長その他の執行機関は,権利委員会からの答申を尊重し,必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は,前条の規定による答申及び前項の規定により講じた措置について公表するものとする。
「射水氏こども条例」
[射水市子どもに関する施策推進委員会が設置され、推進計画を策定]
■(推進計画)
第10条 市は、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、射水市子どもに関する施策推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画を策定するに当たっては、第11条第1項に規定する射水市子ども施策推進委員会の意見を聴くとともに、広く市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。
[射水市少子化対策及び子ども施策に関する推進計画にかかるアンケート調査]毎年実施
■(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。
「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」
[オンブズパーソンより毎年報告書が公表される]
■(運営状況等の報告及び公表)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況等について、市長に文書で報告するとともに、これを公表するものとする。
(子ども及び市民への広報等)
第21条 市の機関は、子ども及び市民にこの条例の趣旨及び内容を広く知らせるとともに、子どもがオンブズパーソンへの相談並びに擁護及び救済の申立てを容易に行うことができるため必要な施策の推進に努めるものとする。
「秋田県子ども・子育て支援条例」
[子ども・子育て支援について基本的な計画を本条例に基づき定めるとしている]
■第二章 基本的施策
(基本計画)
第八条 知事は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子ども・子育て支援に関する目標及び施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための重要事項
「高知県子ども条例」
[高知県子どもの環境づくり推進委員会の設置により推進計画の策定を義務付けている]
■第10条 県は、この条例の目的及び基本理念を実現するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき指針
(2) 前号に掲げるもののほか、子どもの環境づくりに関する取組を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
高知県子ども条例[施策推進委員会の定義あり]
■(推進委員会の設置等)
第11条 子どもの環境づくりに関する施策を推進するため、高知県子どもの環境づくり推進委員会(以下この条において「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 推進計画の作成及び変更に関すること並びにこの条例の目的の実現に関する重要な事項を調査審議すること。
(2) 推進計画に基づき県が実施する子どもの環境づくりに関する取組の状況について、知事に対して意見を述べること。
(広報及び啓発)
第12条 県は、この条例の目的及び基本理念についての理解が促進されるよう、広報及び啓発に努めるものとする。
「三重県子ども条例」
[推進計画の策定義務には言及していないが、施策の基本事項を定めた]
[また、施策実施状況を毎年評価し、年次報告書「みえの子ども白書」を発行]
■(施策の基本となる事項)
第11 条 県は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項の確保を旨とするものとする。
(1)子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提供すること。
(2)子どもに係る施策に関して、子どもが意見を表明する機会を設け、参加を促すとともに、子どもの意見を尊重すること。
(3)子どもが、自らの力を発揮して育つことができるよう、主体的に取り組む様々な活動を支援すること。
(4)子どもの育ちを見守り、及び支えるための人材の育成を行うとともに、保護者、学校関係者等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町が行う活動の促進が図られるよう、環境の整備を行うこと。
(広報及び啓発)
第13 条 県は、子どもの育ちについての県民の関心及び理解を深めるとともに、県民が行う子どもの育ちを見守り、及び支える活動を促進するため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
■(年次報告)
第15 条 知事は、毎年、この条例に基づき県が行う施策の実施状況を評価し、これを年次報告として取りまとめ、公表するとともに、施策への反映に努めるものとする。
条例に基づく調査の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、子どもをとりまく大人の意識や社会の状況などを「みえの子ども白書」として定期的にまとめます。
白書の内容は、子ども、保護者や学校関係者、企業、地域のさまざまな団体、市町・県といった行政などで広く共有し、子どもと大人が理解しあったり、地域で連携して子どもの育ちを支えるための取り組みにつなげたりします。

子ども支援条例のパブリックコメント〆切まであと7日!
長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切まで
あと7日!
「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について、ご意見を募集します
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/251125kossiikenbosyuu.html
長野県HPに、意見提出用紙(ワード形式、PDF形式)のファイルがあります。
<パブコメ拡散お願いの依頼文>
======以下 転送歓迎======
平成25年11月24日
各位
子どものびのびネットワーク
代 表 佐 藤 芳 嗣
事務局長 上 條 剛
ご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より、長野県の子どもの育ちの支援のためにご尽力されていることに心より感謝申し上げます。
さて、私ども「子どものびのびネットワーク」は、平成23年5月7日、子どもの人権条例制定を公約に掲げた阿部守一知事を招いて開催された長野県弁護士会主催の子どもの日記念シンポジウム「子どものびのびプロジェクト-子どもの参加とその支援を考える-」より発足しました。様々な立場で子ども・若者支援を実践している市民団体のメンバー,社会福祉士,弁護士等が個人として参加しています。
長野県は、「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」を設置して子どもの現状と施策について3年間かけて調査し議論し、同委員会からは阿部知事に対して、今年7月に条例に盛り込むべき事項の提出がありました。
<参考>
「最終とりまとめ」平成25年7月29日に知事に提出
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
この冬には長野県議会に子ども条例(名称は未定)条例案が審議される予定です。委員会報告にあった、子ども尊重、子どもの救済が本当にできる条例とすることが大切です。
私たちは子どもたちにとってベストな条例制定を願い、別紙のような県民の声を県政に届ける「子ども条例パブリックコメントPR」を開始することにいたしました。制定されれば、長野県初の子ども支援の総合条例となります。条例検討委員会の委員と子ども支援者も交え、諏訪、長野、松本、上田各地区において、改めて条例の目指す姿について座談会を行ってきました。
ぜひ、みなさまにもパブリックコメントにご協力いただきたく、ご案内申し上げ周知をお願いする次第です。
チラシ等を添付させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、パブリックコメント提出様式の空欄のものは長野県HPからダウンロード可能です
「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/251125kossiikenbosyuu.html
長野県HP 意見提出用紙(ワード形式、PDF形式)のファイルがあります。
問い合わせ先
〒390-0861
長野県松本市蟻ヶ崎一丁目1番52号
ナカヤビル2階 上條剛法律事務所
弁護士 上 條 剛
TEL:0263-34-4466
FAX:0263-34-4467
======以上転送歓迎==パブリックコメントは12月24日必着です======================
これほどまとまって理路整然としたものでなくても、
「子どもの条例が必要だと思います」の一言で良いのでぜひ送ってください。
「こんな条例いらない」そういう組織票も届くと思われますので。
パブコメ例文をアップしました
↓
子どものびのびネットワーク
長野県子ども支援条例パブリックコメント募集チラシ
http://yahoo.jp/box/V8jAdL
子どものびのびネットワーク
長野県子ども支援条例へのパブリックコメント例
http://yahoo.jp/box/_3jYN4

あと7日!
「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について、ご意見を募集します
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/251125kossiikenbosyuu.html
長野県HPに、意見提出用紙(ワード形式、PDF形式)のファイルがあります。
<パブコメ拡散お願いの依頼文>
======以下 転送歓迎======
平成25年11月24日
各位
子どものびのびネットワーク
代 表 佐 藤 芳 嗣
事務局長 上 條 剛
ご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より、長野県の子どもの育ちの支援のためにご尽力されていることに心より感謝申し上げます。
さて、私ども「子どものびのびネットワーク」は、平成23年5月7日、子どもの人権条例制定を公約に掲げた阿部守一知事を招いて開催された長野県弁護士会主催の子どもの日記念シンポジウム「子どものびのびプロジェクト-子どもの参加とその支援を考える-」より発足しました。様々な立場で子ども・若者支援を実践している市民団体のメンバー,社会福祉士,弁護士等が個人として参加しています。
長野県は、「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」を設置して子どもの現状と施策について3年間かけて調査し議論し、同委員会からは阿部知事に対して、今年7月に条例に盛り込むべき事項の提出がありました。
<参考>
「最終とりまとめ」平成25年7月29日に知事に提出
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
この冬には長野県議会に子ども条例(名称は未定)条例案が審議される予定です。委員会報告にあった、子ども尊重、子どもの救済が本当にできる条例とすることが大切です。
私たちは子どもたちにとってベストな条例制定を願い、別紙のような県民の声を県政に届ける「子ども条例パブリックコメントPR」を開始することにいたしました。制定されれば、長野県初の子ども支援の総合条例となります。条例検討委員会の委員と子ども支援者も交え、諏訪、長野、松本、上田各地区において、改めて条例の目指す姿について座談会を行ってきました。
ぜひ、みなさまにもパブリックコメントにご協力いただきたく、ご案内申し上げ周知をお願いする次第です。
チラシ等を添付させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、パブリックコメント提出様式の空欄のものは長野県HPからダウンロード可能です
「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/happyou/251125kossiikenbosyuu.html
長野県HP 意見提出用紙(ワード形式、PDF形式)のファイルがあります。
問い合わせ先
〒390-0861
長野県松本市蟻ヶ崎一丁目1番52号
ナカヤビル2階 上條剛法律事務所
弁護士 上 條 剛
TEL:0263-34-4466
FAX:0263-34-4467
======以上転送歓迎==パブリックコメントは12月24日必着です======================
これほどまとまって理路整然としたものでなくても、
「子どもの条例が必要だと思います」の一言で良いのでぜひ送ってください。
「こんな条例いらない」そういう組織票も届くと思われますので。
パブコメ例文をアップしました
↓
子どものびのびネットワーク
長野県子ども支援条例パブリックコメント募集チラシ
http://yahoo.jp/box/V8jAdL
子どものびのびネットワーク
長野県子ども支援条例へのパブリックコメント例
http://yahoo.jp/box/_3jYN4

詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)
パブリックコメントのポイント
【骨子案修正のポイント】
●子ども支援委員は最低3人「以上」が当然ではないか。らさに、圏域の推薦で+4人と考えるのが自然。
●第三者性を確保できる事務局機能、オンブズパーソン機能を持つ子ども相談・調査専門員の設置を復活させること
●地域子ども支援者の支援機能を復活。子ども施策の全県的施策評価に基づいて必要な施策を立てると定義。
【長野県子ども支援条例骨子案を見てみよう~弱い委員会体制~】
6章相談・救済
(1)子どもの相談に応じる総合的な窓口
子どもの相談に応じる総合的な窓口を設置し、次に掲げる業務を行います。
① 子ども自身の悩み及び子どもに関する様々な問題について、相談に応じること。
② 市町村、学校等関係者等に対する子ども支援に関する助言その他の支援を行うこと。
(2)子ども支援委員会(仮称)
1)組 織
(ア)委員会は、3人以内(予定)で組織する。
(イ)委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。
(2)特別委員
(ア)委員会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことがで
きる。
(イ)特別委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。
【しくみを考える委員会の答申ではどうであったか】
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
1 子ども支援センター(仮称)の設置
・県は、子どもの最善の利益を図るため、子ども固有の相談・救済のしくみを「第三者機関」とし
て知事部局に設置すべきと考える。
・第三者機関は、次の 2 つの役割を担う必要がある。
● 相談・救済(個別救済と提言)
● 地域子ども支援(地域における子ども支援のネットワーク化)
・教育委員会内に設置されている「こどもの権利支援センター」を改編、拡充し、当該第三者機関
とすることが望ましい。
2 相談・救済
子ども支援委員(仮称)および子ども相談・調査専門員(仮称)の設置
・子ども支援センターに、「相談・救済」のしくみとして、子ども支援委員及び子ども相談・調査専
門員を置く。
・子ども支援委員は、子どもの人権救済や回復のために助言や支援を行う。
・子ども支援委員は、救済の申立てを受けたとき、又は自らの発意により、必要に応じて調査、調
整、勧告、意見表明及び是正要請をする。
・勧告、意見表明及び是正要請に関しては、とられた措置の報告を求めることができ、必要と認め
るときは、その内容を公表する。
・子ども相談・調査専門員は、子どもなどからの相談に応じるとともに、子ども支援委員の職務、
活動を補助する。
・子ども相談・調査専門員の任命にあたっては、増加する発達障がいなど特別支援に対応できる人
材の確保に配慮する
【どこかに行ってしまったのは何か?】
●相談機関の第三者性・・・総合的に相談をするとだけされて、子どもの立場に立って救済するとは約束しない。
●地域子ども支援(地域における子ども支援のネットワーク化) ・・・ネットワークというカタカナを嫌っただけでなく、「支援」そのものの内容を「助言」レベルまで軽くしてしまっている。
「支援」と言われると、ヒトモノカネを出す印象を受けるけど、それを出せないから「助言」にした?
●子どもに寄り添い相談に乗る「子ども相談・調査専門員」のカット・・・ 子ども支援委員は全県を見渡せるスーパーバイザーのような位置づけ、そこに子どもをつなげてくる、子どもの相談調整にあたる伴走者としての「子ども相談・専門調査員」が丸々なくなることで、残された子ども支援委員が単なる「○○審議会」のような書類審査機能になってしまう。
●子どもの特別のニーズに対応できる人材を子ども・調査専門委員に任命するはずが・・・たとえば、障害がある子どもが受けた体罰について誰が相談を聴くか。子どもが表出する問題行動を子どものSOSとしてキャッチできるか。
●子ども支援委員会が3人(以下)でできることは何か・・・申し立て書類を書かせて、結果通知を本人や関係者に出すような機構図になっている。きわめて大人向けの救済機能の形。
【他自治体の条例概観】
長野県に同じく3人「以下」と定義しているのは松本市だけであるが、松本市は委員の補佐としての調査相談員を置くとしている。また松本市は施策評価機能として子どもにやさしいまちづくり委員会を設置。まちづくり委員会は定員15人以下とさだめる。
物理的広さも考え合わせると長野県に3人以下でなぜ事足りるのか。
「松本市子どもの権利に関する条例」
2 擁護委員の定数は、3人以内とします。
5 市は、擁護委員の職務を補佐するため、調査相談員を置きます。
2 市は、推進計画をつくるときには、子どもをはじめ市民や、第23条に定める松本市子どもにやさしいまちづくり委員会の意見を聴きます。
3 市は、推進計画及びその進行状況について、広く市民に公表します。
(子どもにやさしいまちづくり委員会)
第23条 2 委員会の委員は、15人以内とします。
3 委員は、人権、健康、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。
「高知県子ども条例」
3 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、子どもに関し識見のある15歳以上の子どもを含む県民から、知事が任命する。
「埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」
(委員会の組織等)
第四条 委員会は、委員三人をもって組織する。
「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」
第5条 オンブズパーソンの定数は、3人以上5人以下とする。
3 オンブズパーソンは、人格が高潔で、社会的信望が厚く、子どもの人権問題に関し優れた識見を有する者で、次条に規定するオンブズパーソンの職務の遂行について利害関係を有しないもののうちから、市長が委嘱する。
「川崎市子どもの権利に関する条例」
3 権利委員会は,委員10人以内で組織する。
4 委員は,人権,教育,福祉等の子どもの権利にかかわる分野において学識経験のある者及び市民のうちから,市長が委嘱する。
5 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
【骨子案修正のポイント】
●子ども支援委員は最低3人「以上」が当然ではないか。らさに、圏域の推薦で+4人と考えるのが自然。
●第三者性を確保できる事務局機能、オンブズパーソン機能を持つ子ども相談・調査専門員の設置を復活させること
●地域子ども支援者の支援機能を復活。子ども施策の全県的施策評価に基づいて必要な施策を立てると定義。
【長野県子ども支援条例骨子案を見てみよう~弱い委員会体制~】
6章相談・救済
(1)子どもの相談に応じる総合的な窓口
子どもの相談に応じる総合的な窓口を設置し、次に掲げる業務を行います。
① 子ども自身の悩み及び子どもに関する様々な問題について、相談に応じること。
② 市町村、学校等関係者等に対する子ども支援に関する助言その他の支援を行うこと。
(2)子ども支援委員会(仮称)
1)組 織
(ア)委員会は、3人以内(予定)で組織する。
(イ)委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。
(2)特別委員
(ア)委員会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことがで
きる。
(イ)特別委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。
【しくみを考える委員会の答申ではどうであったか】
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
1 子ども支援センター(仮称)の設置
・県は、子どもの最善の利益を図るため、子ども固有の相談・救済のしくみを「第三者機関」とし
て知事部局に設置すべきと考える。
・第三者機関は、次の 2 つの役割を担う必要がある。
● 相談・救済(個別救済と提言)
● 地域子ども支援(地域における子ども支援のネットワーク化)
・教育委員会内に設置されている「こどもの権利支援センター」を改編、拡充し、当該第三者機関
とすることが望ましい。
2 相談・救済
子ども支援委員(仮称)および子ども相談・調査専門員(仮称)の設置
・子ども支援センターに、「相談・救済」のしくみとして、子ども支援委員及び子ども相談・調査専
門員を置く。
・子ども支援委員は、子どもの人権救済や回復のために助言や支援を行う。
・子ども支援委員は、救済の申立てを受けたとき、又は自らの発意により、必要に応じて調査、調
整、勧告、意見表明及び是正要請をする。
・勧告、意見表明及び是正要請に関しては、とられた措置の報告を求めることができ、必要と認め
るときは、その内容を公表する。
・子ども相談・調査専門員は、子どもなどからの相談に応じるとともに、子ども支援委員の職務、
活動を補助する。
・子ども相談・調査専門員の任命にあたっては、増加する発達障がいなど特別支援に対応できる人
材の確保に配慮する
【どこかに行ってしまったのは何か?】
●相談機関の第三者性・・・総合的に相談をするとだけされて、子どもの立場に立って救済するとは約束しない。
●地域子ども支援(地域における子ども支援のネットワーク化) ・・・ネットワークというカタカナを嫌っただけでなく、「支援」そのものの内容を「助言」レベルまで軽くしてしまっている。
「支援」と言われると、ヒトモノカネを出す印象を受けるけど、それを出せないから「助言」にした?
●子どもに寄り添い相談に乗る「子ども相談・調査専門員」のカット・・・ 子ども支援委員は全県を見渡せるスーパーバイザーのような位置づけ、そこに子どもをつなげてくる、子どもの相談調整にあたる伴走者としての「子ども相談・専門調査員」が丸々なくなることで、残された子ども支援委員が単なる「○○審議会」のような書類審査機能になってしまう。
●子どもの特別のニーズに対応できる人材を子ども・調査専門委員に任命するはずが・・・たとえば、障害がある子どもが受けた体罰について誰が相談を聴くか。子どもが表出する問題行動を子どものSOSとしてキャッチできるか。
●子ども支援委員会が3人(以下)でできることは何か・・・申し立て書類を書かせて、結果通知を本人や関係者に出すような機構図になっている。きわめて大人向けの救済機能の形。
【他自治体の条例概観】
長野県に同じく3人「以下」と定義しているのは松本市だけであるが、松本市は委員の補佐としての調査相談員を置くとしている。また松本市は施策評価機能として子どもにやさしいまちづくり委員会を設置。まちづくり委員会は定員15人以下とさだめる。
物理的広さも考え合わせると長野県に3人以下でなぜ事足りるのか。
「松本市子どもの権利に関する条例」
2 擁護委員の定数は、3人以内とします。
5 市は、擁護委員の職務を補佐するため、調査相談員を置きます。
2 市は、推進計画をつくるときには、子どもをはじめ市民や、第23条に定める松本市子どもにやさしいまちづくり委員会の意見を聴きます。
3 市は、推進計画及びその進行状況について、広く市民に公表します。
(子どもにやさしいまちづくり委員会)
第23条 2 委員会の委員は、15人以内とします。
3 委員は、人権、健康、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。
「高知県子ども条例」
3 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、子どもに関し識見のある15歳以上の子どもを含む県民から、知事が任命する。
「埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」
(委員会の組織等)
第四条 委員会は、委員三人をもって組織する。
「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」
第5条 オンブズパーソンの定数は、3人以上5人以下とする。
3 オンブズパーソンは、人格が高潔で、社会的信望が厚く、子どもの人権問題に関し優れた識見を有する者で、次条に規定するオンブズパーソンの職務の遂行について利害関係を有しないもののうちから、市長が委嘱する。
「川崎市子どもの権利に関する条例」
3 権利委員会は,委員10人以内で組織する。
4 委員は,人権,教育,福祉等の子どもの権利にかかわる分野において学識経験のある者及び市民のうちから,市長が委嘱する。
5 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
パブコメPRキャラバン隊用に当事者の若者が作ってくれたフェルト人形「願い、とどくま」ちゃんと「いっしょに、うごくま」ちゃん(緑)


長野県子ども支援条例骨子案 パブリックコメント募集中
11月25日~12月24日(必着)、「長野県子ども支援条例(仮称)骨子(案)」について意見募集(パブリックコメント)がなされています。
より良い子ども条例を求めて、どしどし意見を出しましょう!

より良い子ども条例を求めて、どしどし意見を出しましょう!
長野県HP
写真は、PRキャラバン隊 マスコットの ねがい、とどくま ちゃん

~長野県の「子ども条例」制定に向けて~」
 参加者募集! 子育て支援者、医療、福祉、教育、もちろん保護者も
参加者募集! 子育て支援者、医療、福祉、教育、もちろん保護者も子どもの育ちを支えるしくみを考えよう!in松本
~長野県の「子ども条例」制定に向けて~」
■日時 2013年11月25日(月) 開場17:30 開会18:00~閉会20:30
■会場 松本市中央公民館(Мウィング)3階ネットワーク室(松本市大手3-8-13)
■主催 子どものびのびネットワーク
■後援 長野県・長野県教育委員会 松本市・松本市教育委員会
■対象 議会・教育・福祉など行政、子ども・若者支援機関、若者や保護者等
■参加費 500円(資料代等)
■事前申込み 不要
■駐車場 松本市役所駐車場等をご利用ください。
■会場 松本市中央公民館(Мウィング)3階ネットワーク室(松本市大手3-8-13)
■主催 子どものびのびネットワーク
■後援 長野県・長野県教育委員会 松本市・松本市教育委員会
■対象 議会・教育・福祉など行政、子ども・若者支援機関、若者や保護者等
■参加費 500円(資料代等)
■事前申込み 不要
■駐車場 松本市役所駐車場等をご利用ください。
Mウィング併設有料駐車場もございます。
■告知/取材/お問い合わせは 子どものびのびネットワーク 事務局長 上條剛まで
電話 0263-34-4466(上條弁護士事務所)
■告知/取材/お問い合わせは 子どものびのびネットワーク 事務局長 上條剛まで
電話 0263-34-4466(上條弁護士事務所)
第1部 基調メッセージ
松本市の「子どもの権利に関する条例」の意義は?
そして、長野県はどんな「子ども条例」を?
講師 荒牧 重人氏(山梨学院大学教授、長野県「子どもの育ちを支えるしくみを
考える委員会」委員、松本市「子どもにやさしいまちづくり委員会」委員長)
松本市の「子どもの権利に関する条例」の意義は?
そして、長野県はどんな「子ども条例」を?
講師 荒牧 重人氏(山梨学院大学教授、長野県「子どもの育ちを支えるしくみを
考える委員会」委員、松本市「子どもにやさしいまちづくり委員会」委員長)
第2部 ワークショップ
「子どもの権利について語り合い、理解を深めましょう!」
コメンテーター:○上條 剛氏(子どものびのびネットワーク事務局長)
○北川 和彦氏(松本市の相談室「こころの鈴」権利擁護委員)
○神津 ゆかり氏(元「松本市子どもの権利検討委員会」委員)
ファシリテーター(全体進行):中村 健(子どものびのびネットワーク)
<座談会in松本 趣旨>
「子どものびのびネットワーク」って何? ―長野県弁護士会では、子どもの人権条例制定を公約に掲げた阿部守一知事を招いて、平成23年5月7日、子どもの日記念シンポジウム「子どものびのびプロジェクト-子どもの参加とその支援を考える-」を開催しました。そこに様々な立場で子ども・若者支援を実践している市民団体のメンバー、社会福祉士、弁護士等が個人として集い、「子どものびのびネットワーク」が発足しました。
長野県では、子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会を平成23年に県子ども家庭課に設置し、子どもの実態調査を実施するなど、3か年の事業で子どもの育ちをささえるしくみの検討に入っています。この冬には、長野県議会に長野県子ども人権条例(名称は未定)の条例案が提出され審議される予定です。私達はこの条例が長野県の子どもたちにベストのものとなることを願い、PRする活動を開始しました。議会、教育、福祉などの行政の垣根を超えて、地域でこの条例について語り合う座談会を諏訪、松本、長野で開催します。県民主体の条例制定をめざしましょう。
子どものびのびネットワーク 代 表 佐藤 芳嗣(佐藤芳嗣法律事務所)
子どものびのびネットワークお問い合わせ 事務局長 上條 剛 (上條剛法律事務所)
「子どもの権利について語り合い、理解を深めましょう!」
コメンテーター:○上條 剛氏(子どものびのびネットワーク事務局長)
○北川 和彦氏(松本市の相談室「こころの鈴」権利擁護委員)
○神津 ゆかり氏(元「松本市子どもの権利検討委員会」委員)
ファシリテーター(全体進行):中村 健(子どものびのびネットワーク)
<座談会in松本 趣旨>
「子どものびのびネットワーク」って何? ―長野県弁護士会では、子どもの人権条例制定を公約に掲げた阿部守一知事を招いて、平成23年5月7日、子どもの日記念シンポジウム「子どものびのびプロジェクト-子どもの参加とその支援を考える-」を開催しました。そこに様々な立場で子ども・若者支援を実践している市民団体のメンバー、社会福祉士、弁護士等が個人として集い、「子どものびのびネットワーク」が発足しました。
長野県では、子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会を平成23年に県子ども家庭課に設置し、子どもの実態調査を実施するなど、3か年の事業で子どもの育ちをささえるしくみの検討に入っています。この冬には、長野県議会に長野県子ども人権条例(名称は未定)の条例案が提出され審議される予定です。私達はこの条例が長野県の子どもたちにベストのものとなることを願い、PRする活動を開始しました。議会、教育、福祉などの行政の垣根を超えて、地域でこの条例について語り合う座談会を諏訪、松本、長野で開催します。県民主体の条例制定をめざしましょう。
子どものびのびネットワーク 代 表 佐藤 芳嗣(佐藤芳嗣法律事務所)
子どものびのびネットワークお問い合わせ 事務局長 上條 剛 (上條剛法律事務所)
子どもの育ちを支えるしくみを考える座談会in長野 開催
 子どもの育ちを支えるしくみを考える座談会in長野
子どもの育ちを支えるしくみを考える座談会in長野全ての子どもが安心して生きる、育つために
~長野県子ども人権条例を語ろう~
日時 2013年11月11日(月) 開場17時半 開会18時~閉会20時
会場 長野県弁護士会館4階会議室(長野市妻科432)
主催 子どものびのびネットワーク
後援 長野市 長野県 長野県教育委員会
内容 参加費無料
座談会「長野県子ども支援条例(仮称)の行方
―県民・子ども参加で創ろう!」
講師 早稲田大学教授 喜多明人先生
(長野県子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会委員長)
グループ討議「長野県の子ども支援条例(仮称)について」
コーディネーター 弁護士 北川和彦先生
(長野県子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会副委員長)
資料(別添)喜多先生資料
イラストパンフ「子どもの育ちを支える」、パブリックコメントPRチラシ
対象 議会、教育、福祉など行政、子ども・若者支援機関、若者や保護者等
<座談会in長野 趣旨>
「子どものびのびネットワーク」って何? ―長野県弁護士会では、子どもの人権条例制定を公約に掲げた阿部守一知事を招いて、平成23年5月7日、子どもの日記念シンポジウム「子どものびのびプロジェクト-子どもの参加とその支援を考える-」を開催しました。そこに様々な立場で子ども・若者支援を実践している市民団体のメンバー、社会福祉士、弁護士等が個人として集い、「子どものびのびネットワーク」が発足しました。
長野県では、子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会を平成23年に県子ども家庭課に設置し、子どもの実態調査を実施するなど、3か年の事業で子どもの育ちをささえるしくみの検討に入っています。この冬には、長野県議会に長野県子ども人権条例(名称は未定)の条例案が提出され審議される予定です。私達はこの条例が長野県の子どもたちにベストのものとなることを願い、PRする活動を開始しました。議会、教育、福祉などの行政の垣根を超えて、地域でこの条例について語り合う座談会を諏訪、松本、長野で開催します。県民主体の条例制定をめざしましょう。
子どものびのびネットワーク 代 表 佐藤 芳嗣(佐藤芳嗣法律事務所)
子どものびのびネットワークお問い合わせ 事務局長 上條 剛 (上條剛法律事務所)
TEL:0263-34-4466 FAX:0263-34-3367
長野県松本市蟻ヶ崎一丁目1番52号
座談会講師 喜多明人(きた・あきと) ―「子ども支援とまちづくり」が研究活動のテーマ。日本教育法学会理事。子どもの権利条約ネットワーク(NCRC)代表。長野県子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会委員長。
主な著書には『子どもにやさしいまちづくり-自治体子ども施策の現在とこれから』(2004年・日本評論社・共編著)、「現代学校改革と子どもの参加の権利」(2003年・学文社・編著)などがあります。
<開催報告>
1 座談会「長野県子ども支援条例(仮称)の行方
―県民・子ども参加で創ろう!」
講師 早稲田大学教授 喜多明人先生
(長野県子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会委員長)
・ 平成23年6月から3年間の「長野県子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」で議論、子ども条例制定を求める委員会最終取りまとめを平成25年7月19日に阿部知事に提出。条例制定が必要ということと、条例に盛り込むべき事項について提言。
・ 同委員会の子ども部会(SKIP・信州子どもと一緒にプロジェクト)では、子どもたち自身の話し合いから「子どもの力を信頼し、まかせて欲しい」「私たち子どもの話を最後まで聴いて欲しい」「安心して相談できる場がない」等を訴える提言書がまとめられた。
・ また、県内各地から一同に会して話し合いをするには、東西南北に広い長野県を痛感。子どもに身近な地域に相談窓口を置くことが必要。
・ 委員会で、条例の骨子とすべき事項として提言したのは
「子ども支援とは何かの定義」
「子どもの相談救済のための、子ども支援センター(知事直轄の相談センター)と子ども支援委員会(第三者機関)」
「出生時から大人までを継続した子どもの育ちの支援」
「子どもを支えている支援者への支援」
「実際に救済機関が機能するための子ども達や市町村への普及、周知」
地域での子どもの権利支援と、子どもの権利救済の二本立ての構成とした。
・ 現在は、子ども家庭課の事務局で条例案の骨子を作成中。また、法令担当の課でなかなか厳しいチェックを受けている状態。三重県はじめ、他の自治体でも多く採用されているメッセージ性の強い前文などを要望したが、前例がないとのことで却下されているとのこと。前例主義からの脱却が必要ではないか。
・ 子どもへの支援と、子どもを支える地域資源への支援との2方面への支援を理念としたのは、松本市子どもの権利条例と同じ画期的な形で、全国的にはめずらしく、長野県方式と言える。対象的なのが東京都の青少年健全育成条例であり、厳罰化・ゼロトレランス方式を採用しているが、管理主義は聞こえが良いが(罰を厳しくすれば問題が減るような印象を受ける)、子どもの現場はそんなに単純なものではなく、効果に乏しい。
・ 今後、2月県議会に条例を提案し、成立の予定であり、その前にパブリックコメントが行われる。当初の予定より遅れ、11月下旬ごろ開始か。委員会の提案から後退してしまう部分を心配している。多くの子ども支援者から、子どもの現状に即した意見を積極的に届ける必要がある。
・ 子ども条例、子どもの権利条例は多くの地方自治体の議会で、全会一致で成立してきている。長野でも全会一致を目指している。今回の座談会は、諏訪、長野で開催、今後松本で開催が決まっている。県民による議論で、ぜひ全会一致の議会採択へ進んでいって欲しい。
2 グループ討議「長野県の子ども条例について」
コーディネーター 弁護士 北川和彦先生
(長野県子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会副委員長)
子ども条例についての思い、盛り込むべき内容について、4~6人組みになりテーブル毎で討議を実施。各グループより報告を得た。
【Aグループ】
・ 子ども支援センターは「地域」「子ども」「社会」をつなげていく役割を担っている。現場全体をわかっている人がコーディネーター役として必要。
【Bグループ】
・ 子どもの身近に相談できる居場所を。 公のところに相談したが、あくまで学校の立場で助言されてしまって、相談しても先が見えなかった。公でも、民間の資源・取り組みとつながって、相談者をつなげて欲しい。いろんな機関があるけれど、つながって欲しい。
【Cグループ】
・ 条例に反対の人には、子どもの現実が今どんな状態かを把握してもらうところから意見交換をしていくことが必要。人権を保障することは決してワガママの助長ではない。
・ 公の相談機関には、個人情報を伝えることのためらいがあり、相談へのハードルとなっている。
・ 児童相談所は虐待対等で余裕がなくなっている。相談者(親子)の気持ちをゆっくり話せる場所が必要。
【Dグループ】
・ 子ども観を伝えられる条例に。
・ 子どもも人格を持った人間として、大切にされる、認められる中で、自ら考えることができる。自ら話して、相談できる「相談力」をはぐくむことが必要。長野の子どもアンケートでは、大人から暴力、周囲からいじめを受けて辛い時に、「(相談しないで)がまんする」という子が3割あった。
【Eグループ】
・ 小学校段階で、進路に向き合い、考えざるを得ない時代になった。親も悩んでいる。相談先を。
【Fグループ】
・ 10年前より、教員の同僚性が失われてきてしまっている。多忙化の課題がある。
・ 児童相談所の専門性も下がってきてしまっていると感じる。専門家の配置が課題では。
【Gグループ】
・ いじめは悪意がなく原因もなく始まる場合もある。子どもが自分の気持ちを言葉で話せること、大人が子どもの気持ちを受け止められることが重要。「気持ちを言葉で伝えていいんだよ」ということを子どもに知ってもらう。(人権尊重)
【Hグループ】
・ チャイルドラインへの2万件の電話。いじめ、不登校、虐待など子どもが逃げたい時に子ども自身が駆け込める場所が地域にあるだろうか。
・ 子どもの支援センターは子どもに身近な居場所に必要。安心できる枠組みに。独立した第三者機関であることも重要。
【Iグループ】
・ 経済的、貧困問題を抱えている子どもが沢山いる。今までの学校のやり方に限界も。
・ 子どもが疎外状態の時に、その子の親御さんも地域の中で居場所を無くしている場合が往々にしてある。
・ 中学生にとっては、たまり場が消滅。部活に所属できないときに、公園で遊んでいるだけで中学校に通報が来る(幼児が遊ぶのに支障があると)。ゲームセンターに行く子は、他に居場所がなくて徘徊している。
・ 子どもの居場所になるような公園が少ない。
・ 学校と、家庭だけでは足りない。そこに居場所がない時もある。子どもにとってのもう一つの居場所が大切。
イラスト版 子ども人権条例パンフレット
子どものびのびネットワークでは、この秋長野県で審議される長野県子ども人権条例が、長野県の子どもたちにとってベストのものとなることを願って活動しています。
今回、「長野県子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会」から長野県知事に対して出された最終報告書を下敷きに、子ども人権条例の理念を分かりやすくまとめたパンフレットを市民案として作成しました。
パブリックコメントの作成の際にお使いください。また、子どもの人権ってなあに? ということを、周りの大人にも、子どもにも、広く伝えていきましょう。
子ども人権条例パンフレット
制作:子どものびのびネットワーク
「イラスト版 子どもの育ちを支えるしくみを考える」
ページ1 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/EWVmhm
「どうしたら子どもを支えられる?」
・長野県が平成24年に実施した子どもアンケートでは、いじめられた子どもの3割、大人から暴力を受けた子どもの6割が「がまんした」と回答しています。
・子ども部会SKIPの報告では、大人への願いとして、「怒りたくなる話でも、冷静に最後まで聴いていて欲しい」「注意の理由を言って欲しい」「比べないで」・・・子どもの声を聞いて欲しいと言う意見表明がされました。
・どんなに困っていても、「どうせ自分なんて」自己肯定感が低くなってしまうと、相談する力が湧きません。
・いじめ、不登校、自殺、非行・・・話せない言葉も、大人から見れば問題行動も、本当は子どもからのSOSです。
ページ2 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/2yZ08d
「大切な子どもたちへ」
・今、大人がみんなで取り組むことは
「あなたのSOSを聴くよ」
「強い人や大勢の人が、弱い人や一人の人への暴力を許さないよ」
「誰が悪いかを罰するのではなく、お互いの人権を尊重しあえる新しい関係を作っていくよ」
・子どもと一緒に未来を創るため、長野県は子どもの声を聴く条例を作ります。
ページ3 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/jjZQNk
「子どもの人権が守られるってこんなこと」
・安心して成長できること、自身を持ってチャレンジできること、自由に意見が言えること
・「子どもにも人権がある」と世界中の193の国が子ども権利条約で約束をした。もちろん、長野県のあなたも、誕生の瞬間から人権を持っている。
・自分の人権を守るために「相談する」ことは、「告げ口」じゃないんだ。
・自分の権利を大切に守れると、相手の権利も大切にできるようになるよ。
ページ4 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/0IZ6k2
「長野に生まれて、長野に育って、幸せだと思える 全ての子に居場所と出番のある地域づくりをする」
・充分に悩んだ子が、誰かの相談を受け止められる大人になる。
・失敗を経験した子が、誰かを助けてあげられる大人になる。
・人権を尊重された子が、周囲の人を尊重できる大人になる。
・子どもが自分を信じて、生き抜くことを支えます。
Q&A「体罰やいじめの加害者には、有無を言わせず厳罰で臨むことが必要では?」
「子どもは大人が守り、教える対象であり、自由にさせたら自己中心でわがままになるだけでは?」
参考文献
1. ユニセフ 子どもの権利条約特設サイト
http://www.unicef.or.jp/crc/index.html
2. あなたが守る、あなたの心、あなたのからだ
森田ゆり著 童話堂出版
3. 見逃さないで! 子どもの心のSOS 思春期にがんばっている子
明橋大二著 1万年堂出版
4. 長野県子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会 最終報告 2013年7月
今回、「長野県子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会」から長野県知事に対して出された最終報告書を下敷きに、子ども人権条例の理念を分かりやすくまとめたパンフレットを市民案として作成しました。
パブリックコメントの作成の際にお使いください。また、子どもの人権ってなあに? ということを、周りの大人にも、子どもにも、広く伝えていきましょう。
子ども人権条例パンフレット
制作:子どものびのびネットワーク
「イラスト版 子どもの育ちを支えるしくみを考える」
ページ1 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/EWVmhm
「どうしたら子どもを支えられる?」
・長野県が平成24年に実施した子どもアンケートでは、いじめられた子どもの3割、大人から暴力を受けた子どもの6割が「がまんした」と回答しています。
・子ども部会SKIPの報告では、大人への願いとして、「怒りたくなる話でも、冷静に最後まで聴いていて欲しい」「注意の理由を言って欲しい」「比べないで」・・・子どもの声を聞いて欲しいと言う意見表明がされました。
・どんなに困っていても、「どうせ自分なんて」自己肯定感が低くなってしまうと、相談する力が湧きません。
・いじめ、不登校、自殺、非行・・・話せない言葉も、大人から見れば問題行動も、本当は子どもからのSOSです。
ページ2 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/2yZ08d
「大切な子どもたちへ」
・今、大人がみんなで取り組むことは
「あなたのSOSを聴くよ」
「強い人や大勢の人が、弱い人や一人の人への暴力を許さないよ」
「誰が悪いかを罰するのではなく、お互いの人権を尊重しあえる新しい関係を作っていくよ」
・子どもと一緒に未来を創るため、長野県は子どもの声を聴く条例を作ります。
ページ3 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/jjZQNk
「子どもの人権が守られるってこんなこと」
・安心して成長できること、自身を持ってチャレンジできること、自由に意見が言えること
・「子どもにも人権がある」と世界中の193の国が子ども権利条約で約束をした。もちろん、長野県のあなたも、誕生の瞬間から人権を持っている。
・自分の人権を守るために「相談する」ことは、「告げ口」じゃないんだ。
・自分の権利を大切に守れると、相手の権利も大切にできるようになるよ。
ページ4 PDFファイル→ http://yahoo.jp/box/0IZ6k2
「長野に生まれて、長野に育って、幸せだと思える 全ての子に居場所と出番のある地域づくりをする」
・充分に悩んだ子が、誰かの相談を受け止められる大人になる。
・失敗を経験した子が、誰かを助けてあげられる大人になる。
・人権を尊重された子が、周囲の人を尊重できる大人になる。
・子どもが自分を信じて、生き抜くことを支えます。
Q&A「体罰やいじめの加害者には、有無を言わせず厳罰で臨むことが必要では?」
「子どもは大人が守り、教える対象であり、自由にさせたら自己中心でわがままになるだけでは?」
参考文献
1. ユニセフ 子どもの権利条約特設サイト
http://www.unicef.or.jp/crc/index.html
2. あなたが守る、あなたの心、あなたのからだ
森田ゆり著 童話堂出版
3. 見逃さないで! 子どもの心のSOS 思春期にがんばっている子
明橋大二著 1万年堂出版
4. 長野県子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会 最終報告 2013年7月
子ども人権条例パブリックコメントPR ~よりよい条例づくりのために、住民の声を県政に届けよう~
子どものびのびネットワーク 子ども条例PR
~よりよい条例づくりのために、住民の声を県政に届けよう~
子どものびのびネットワークでは、この秋に長野県議会で審議される長野県子ども条例が、長野県の子どもたちにとってベストのものとなることを願って、子ども条例PR活動を開始しました。
一人でも多くの方にこの条例について関心を持ってもらい、地域で語り合い、住民主体の条例制定をめざしましょう。
<長野県パブリックコメントについて>
・長野県初の子ども条例です。住民の声を反映させ、条例に魂を吹き込みましょう。
・長野県公式ホームページに子ども条例の骨子案と、パブコメの募集概要が掲載されます。
「子どもの育ちを支えるしくみに関する条例(仮称)骨子案について」 (9月パブリックコメント募集予定)
長野県ホームページ
http://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/public/index.html
・しめきりに注意! 募集期間内に、郵便、ファクシミリ、電子メールで担当課に送ります。
FAX:026-235-7390
E-mail: kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp
・県ホームページおよび地方事務所で意見提出用紙が公開されます。
・提出したご意見は、県で計画等に反映できるか充分検討された上で、ご意見の概要とこれに対する県の考え方が県ホームページで公表されます。
・この条例案は、秋の(9月、11月)県議会で議論される予定とのことです。
例えば―――
・子ども人権条例をつくって、困っている子どもの相談をしっかり受け止め、安心して生きる、育つことのできる長野県にしてください。
・子ども人権条例をつくって、学校の先生、児童福祉施設の先生、保護者を始めとした子どもの育ちを支えている大人を、しっかり支えてください。
・子ども人権条例をつくって、教育、保育、医療、福祉…、タテ割りだけでなくヨコでつながる県行政を実現して、子どもの権利条約の理念である「子どもの最善の利益の実現(チルドレンファースト)」に取り組む長野県にしてください。
―――その他、子どもの育ちについてのあなたの
大切な「思い」を言葉にして意見表明しましょう。
★県庁へのパブリックコメントだけでなく、お知り合いの県会議員さんにもお送りください。
<子どものびのびネットワーク いままでの活動>
「子どものびのびプロジェクト -子どもの参加とその支援を考えるーシンポジウム」 実施 (H23.5.6)
県知事へ子どもの権利条例制定への要望書の提出(H23.8.8)(H23.12.22)(H24.7.20)
条例骨子案が示され、議題に提出となることをうけ、パブリックコメントをひろめるアクションを開始
(H25.8月~)
子ども人権条例パブリックコメントPRチラシ ダウンロードはこちらから↓
http://yahoo.jp/box/DGJMAk
~よりよい条例づくりのために、住民の声を県政に届けよう~
子どものびのびネットワークでは、この秋に長野県議会で審議される長野県子ども条例が、長野県の子どもたちにとってベストのものとなることを願って、子ども条例PR活動を開始しました。
一人でも多くの方にこの条例について関心を持ってもらい、地域で語り合い、住民主体の条例制定をめざしましょう。
<長野県パブリックコメントについて>
・長野県初の子ども条例です。住民の声を反映させ、条例に魂を吹き込みましょう。
・長野県公式ホームページに子ども条例の骨子案と、パブコメの募集概要が掲載されます。
「子どもの育ちを支えるしくみに関する条例(仮称)骨子案について」 (9月パブリックコメント募集予定)
長野県ホームページ
http://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/public/index.html
・しめきりに注意! 募集期間内に、郵便、ファクシミリ、電子メールで担当課に送ります。
FAX:026-235-7390
E-mail: kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp
・県ホームページおよび地方事務所で意見提出用紙が公開されます。
・提出したご意見は、県で計画等に反映できるか充分検討された上で、ご意見の概要とこれに対する県の考え方が県ホームページで公表されます。
・この条例案は、秋の(9月、11月)県議会で議論される予定とのことです。
例えば―――
・子ども人権条例をつくって、困っている子どもの相談をしっかり受け止め、安心して生きる、育つことのできる長野県にしてください。
・子ども人権条例をつくって、学校の先生、児童福祉施設の先生、保護者を始めとした子どもの育ちを支えている大人を、しっかり支えてください。
・子ども人権条例をつくって、教育、保育、医療、福祉…、タテ割りだけでなくヨコでつながる県行政を実現して、子どもの権利条約の理念である「子どもの最善の利益の実現(チルドレンファースト)」に取り組む長野県にしてください。
―――その他、子どもの育ちについてのあなたの
大切な「思い」を言葉にして意見表明しましょう。
★県庁へのパブリックコメントだけでなく、お知り合いの県会議員さんにもお送りください。
<子どものびのびネットワーク いままでの活動>
「子どものびのびプロジェクト -子どもの参加とその支援を考えるーシンポジウム」 実施 (H23.5.6)
県知事へ子どもの権利条例制定への要望書の提出(H23.8.8)(H23.12.22)(H24.7.20)
条例骨子案が示され、議題に提出となることをうけ、パブリックコメントをひろめるアクションを開始
(H25.8月~)
子ども人権条例パブリックコメントPRチラシ ダウンロードはこちらから↓
http://yahoo.jp/box/DGJMAk
意識調査フィーバー
長野県ではこどもについての計画をつくる動きが、いまとても熱いです!
 ながの子ども・子育て応援計画(H22年~H26)
ながの子ども・子育て応援計画(H22年~H26)
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/kikaku/shoushika/hagukumi/koukikeikaku.htm
 長野県こども・若者計画(つくり中)
長野県こども・若者計画(つくり中)
「長野県企画部次世代サポート課」のHP
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/support/kashokai.htm
 長野県教育振興基本計画(第一次がH24で終了。第二次をつくり始め)
長野県教育振興基本計画(第一次がH24で終了。第二次をつくり始め)
「学ぶちから・学校力専門委員会」のHP
http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/shingikai/keikaku/
同じく教育委員会で
 特別支援教育推進計画(H23報告書あり 計画はみつからず@@;)
特別支援教育推進計画(H23報告書あり 計画はみつからず@@;)
そしてのびのびネットが取りくんでいる
「こどもの育ちを支える仕組みを考える委員会」
 こども条例づくり
こども条例づくり
http://www.pref.nagano.lg.jp/syakai/seisyounen/kodomonosodati.htm
(議事録、アンケート案など、情報公開丁寧ですが、こども参加にバリアフリーと言えるかどうか・・・)
この計画づくりそれぞれのために、実態調査が何種類も行われるようです。
それぞれの調査を、ぜひヨコワリで活かしてほしいです。
<いままでのアンケート調査>
 児童生徒の生活・学習意識実態調査結果の概要
児童生徒の生活・学習意識実態調査結果の概要
(平成18年7月 教育委員会)
http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/toukei/toukei.htm
 不登校経験者を対象とした学校生活アンケート
不登校経験者を対象とした学校生活アンケート
全日制15校126人、定時制6校241人の不登校経験者に調査
子どもたちは、友達づきあいに深く苦しみ、安心できる居場所を求めていることが浮き彫りになっています。
(平成22年 教育委員会)
「長野県不登校対策検討委員会」
http://www.pref.nagano.jp/kyouiku/kyougaku/futoko/
以下、新聞記事の引用です
~~~~~~~~~~~~~~~
小中高生3000人に意識調査
県「こども・若者応援計画」基礎資料に
学校・家庭での生活状況など
(信濃毎日新聞朝刊 平成23年10月7日4面)
続きを読む
 ながの子ども・子育て応援計画(H22年~H26)
ながの子ども・子育て応援計画(H22年~H26)http://www.pref.nagano.jp/kikaku/kikaku/shoushika/hagukumi/koukikeikaku.htm
 長野県こども・若者計画(つくり中)
長野県こども・若者計画(つくり中)「長野県企画部次世代サポート課」のHP
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/support/kashokai.htm
 長野県教育振興基本計画(第一次がH24で終了。第二次をつくり始め)
長野県教育振興基本計画(第一次がH24で終了。第二次をつくり始め)「学ぶちから・学校力専門委員会」のHP
http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/shingikai/keikaku/
同じく教育委員会で
 特別支援教育推進計画(H23報告書あり 計画はみつからず@@;)
特別支援教育推進計画(H23報告書あり 計画はみつからず@@;)そしてのびのびネットが取りくんでいる
「こどもの育ちを支える仕組みを考える委員会」
 こども条例づくり
こども条例づくりhttp://www.pref.nagano.lg.jp/syakai/seisyounen/kodomonosodati.htm
(議事録、アンケート案など、情報公開丁寧ですが、こども参加にバリアフリーと言えるかどうか・・・)
この計画づくりそれぞれのために、実態調査が何種類も行われるようです。
それぞれの調査を、ぜひヨコワリで活かしてほしいです。
<いままでのアンケート調査>
 児童生徒の生活・学習意識実態調査結果の概要
児童生徒の生活・学習意識実態調査結果の概要(平成18年7月 教育委員会)
http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/toukei/toukei.htm
 不登校経験者を対象とした学校生活アンケート
不登校経験者を対象とした学校生活アンケート全日制15校126人、定時制6校241人の不登校経験者に調査
子どもたちは、友達づきあいに深く苦しみ、安心できる居場所を求めていることが浮き彫りになっています。
(平成22年 教育委員会)
「長野県不登校対策検討委員会」
http://www.pref.nagano.jp/kyouiku/kyougaku/futoko/
以下、新聞記事の引用です
~~~~~~~~~~~~~~~
小中高生3000人に意識調査
県「こども・若者応援計画」基礎資料に
学校・家庭での生活状況など
(信濃毎日新聞朝刊 平成23年10月7日4面)
続きを読む
(読書メモ) 川崎発 子どもの権利条例
自己流読書メモです

「川崎発 子どもの権利条例」
子どもの権利条約 総合研究所編 編集 協力:川崎市
2002年エイブル研究所発行
■概要■
1:逐条解説
「川崎市子どもの権利に関する条例」
2:条例で何が変わるか
「理念と権利保障」「子どもの参加の権利」「子どもからの相談と権利救済」
「子どもの権利に関する行動計画と保障状況の検証」「オンブズパーソン制度」
3:市民参加型条例のこれまでとこれから
「地域教育会議」「市民サロン」「子ども委員会」
4:動き始めた川崎
「川崎市子ども会議(準備会)」「川崎子ども夢パーク」「学校教育推進会議」
「川崎市子どもの権利委員会」
5:資料
「川崎市子どもの権利に関する条例」「川崎市人権オンブズパーソン条例」
「学校教育推進会議・指針・他」「川崎市子どもの権利委員会規則・運営要領」
おまけ 所感
===========================
 1:逐条解説
1:逐条解説
【川崎市子どもの権利に関する条例】抜粋
<前文>
・ 「子ども観」「子どもの権利の理念」の考え方の違いを克服
・ 子どもを「保護される対象」から「自ら権利を行使する主体」へと転換
・ 子どもは権利について学習し、実際に行使することを通して権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任を身につける。
→権利の相互尊重によって「権利と責任(と義務)」の考え方を整理
続きを読む

「川崎発 子どもの権利条例」
子どもの権利条約 総合研究所編 編集 協力:川崎市
2002年エイブル研究所発行
■概要■
1:逐条解説
「川崎市子どもの権利に関する条例」
2:条例で何が変わるか
「理念と権利保障」「子どもの参加の権利」「子どもからの相談と権利救済」
「子どもの権利に関する行動計画と保障状況の検証」「オンブズパーソン制度」
3:市民参加型条例のこれまでとこれから
「地域教育会議」「市民サロン」「子ども委員会」
4:動き始めた川崎
「川崎市子ども会議(準備会)」「川崎子ども夢パーク」「学校教育推進会議」
「川崎市子どもの権利委員会」
5:資料
「川崎市子どもの権利に関する条例」「川崎市人権オンブズパーソン条例」
「学校教育推進会議・指針・他」「川崎市子どもの権利委員会規則・運営要領」
おまけ 所感
===========================
 1:逐条解説
1:逐条解説【川崎市子どもの権利に関する条例】抜粋
<前文>
・ 「子ども観」「子どもの権利の理念」の考え方の違いを克服
・ 子どもを「保護される対象」から「自ら権利を行使する主体」へと転換
・ 子どもは権利について学習し、実際に行使することを通して権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任を身につける。
→権利の相互尊重によって「権利と責任(と義務)」の考え方を整理
続きを読む
子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会(長野県)
子どもの育ち支えるしくみを考える委員会 第一回の委員会が開催され、議事録が公開されました。
(平成23年6月10日 長野県庁 本庁舎3階 特別会議室にて実施)
議事録
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/syakai/seisyounen/kodomonosodati.htm
議事録の一読のまとめは後日配信したいと思っています。
 第二回の委員会が9月16日に開催されます。傍聴できる委員会なので、かけつけて、熱い議論を見守りましょう!
第二回の委員会が9月16日に開催されます。傍聴できる委員会なので、かけつけて、熱い議論を見守りましょう!
以下、長野県のプレスリリース(9月9日)より引用
=======================
第2回 「子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会」
平成23年9月16日(金)午後2時から5時頃まで
長野県庁 議会棟3階 第1特別会議室(長野市大字南長野字幅下692-2)
主な協議内容
(1) 子どもアンケート調査について
(2) 子どもの現状とそれに対する取り組みについて
その他
(1) 会議は公開で行います。
(2) 傍聴者多数の場合、入場をお断りすることがありますのでご了承ください。
=======================..
(平成23年6月10日 長野県庁 本庁舎3階 特別会議室にて実施)
議事録
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/syakai/seisyounen/kodomonosodati.htm
議事録の一読のまとめは後日配信したいと思っています。
 第二回の委員会が9月16日に開催されます。傍聴できる委員会なので、かけつけて、熱い議論を見守りましょう!
第二回の委員会が9月16日に開催されます。傍聴できる委員会なので、かけつけて、熱い議論を見守りましょう!以下、長野県のプレスリリース(9月9日)より引用
=======================
第2回 「子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会」
平成23年9月16日(金)午後2時から5時頃まで
長野県庁 議会棟3階 第1特別会議室(長野市大字南長野字幅下692-2)
主な協議内容
(1) 子どもアンケート調査について
(2) 子どもの現状とそれに対する取り組みについて
その他
(1) 会議は公開で行います。
(2) 傍聴者多数の場合、入場をお断りすることがありますのでご了承ください。
=======================..
「子ども基本条例」制定図る 茅野市 子育て支援で協働促進
子どもを対象にする法律というと、児童福祉法・教育基本法・次世代育成支援対策推進法・・・、○○基本法、△△推進法、と名のつく法律は対策や事業の数だけ無尽蔵に作られているようですが、子ども全体をカバーする、ネットワークのような法律がなかなかない。法律も行政もタテワリにかたよりがちなので、ヨコワリの法律ができることが必要です。茅野市の子ども基本条例、じっくり作っていただきたいです!
以下 新聞記事から引用です
====================
「子ども基本条例」制定図る
茅野市 子育て支援で協働促進
(信毎朝刊平成23年9月14日 4面)
茅野市の柳平千代一市長は13日の市議会9月定例会の一般質問で、来年度中をめどに子育てや教育で市と市民が協働していくための「子ども基本条例」(仮称)の制定を目指す方針を示した。18歳までの子どもの成長や子育てを支援する「子ども・家庭応援計画」の制度的な支えとしたい考え。高校生や大学生らの意見も交え、具体的な中身を検討していく。
同市では、市と市民が協力して施策の企画・立案をし、市民組織が実践する「パートナーシップのまちづくり」を推進。協働の柱とする福祉、環境、教育の3分野のうち、教育分野に基本条例がないことから、制定を図ることになった。
県内では、県や松本市などで子どもの権利条例制定を目指す動きがある。柳平市長は基本条例に盛り込む内容として「子どもの権利に関する内容だけでなく、子育てを通じて親の成長も促したり、読書の普及を進めたりといった内容を総合的に検討する」としている。
県こども・家庭課は「子育て分野に関する基本条例ができれば、県内では珍しいのではないか」としている。
====================
新聞記事 引用おわり
茅野市のホームページより引用です
====================
「こども・家庭応援計画(どんぐりプラン)」
たくましい子ども、やさしい子ども、夢のある子ども
どんぐりプランの誕生
市民が主体となり行政と共に子どもをとりまく諸問題を考えるため、平成9年に福祉21茅野(茅野市の21世紀の福祉を創る会)の分科会として「子育て部会」が発足しました。そこでは、母子保健だけでなく、妊娠中から乳幼児期、学童期を経て18歳になるまで総合的に検討されましたが、福祉21ビーナスプラン(茅野市地域福祉計画)の計画書を提出するにあたり、学童期以降、とりわけ思春期を中心とした時期に対する議論の不足が指摘されました。
そこで福祉21ビーナスプラン策定後、改めて市民ワーキングが組織され、子育て部会、市民ワーキングの考え方を統合し、こども・家庭支援について議論する場として、平成13年に市民34名によって「子ども家庭支援計画策定委員会」が設置されました。 委員会では、行政と共に詳細な議論を重ね「地域ぐるみの子育て・子育ちを応援していくシステム」を構築することを意図として、平成14年に「地域教育福祉計画」である「こども・家庭応援計画(愛称:どんぐりプラン)」をまとめました。
計画の目的
この計画は、子どもが生まれる前から18歳になるまでを一貫して子どもとその家族の子育て・子育ちを応援していくために、生涯学習や学校教育、また保健、医療、福祉といった関連施策を総合的に実施し、掲げられた理念を具現化するために、計画的に推進していくことを目的としています。
計画の基本理念
たくましい子ども、やさしい子ども、夢をもつ子ども
子どもたちが、豊かな自然のなかでさまざまな体験をつみ、人と人との交流のなかでお互いの個性を認め合い、生きる力を育んでいくことを応援します。
様々な課題をもつ子どもや親・家庭には必要な支援をきめ細かく提供していきます。
生命が宿ってから青年期までを教育・保健・医療・福祉が連携して、継続的、総合的な支援をしていきます。
子育ての喜びや大変さを分かちあえるまちを作ります。そのために、地域の教育力を高め、地域の人々が相互に協力して支えていくことを大切にします。
茅野市こども・家庭応援計画(どんぐりプラン)の本編はこちらから
→ http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07010066/07010066.html
====================
全国のこども条例について 調べたい
国際NGO 特定非営利活動法人「子どもの権利条約総合研究所」
→ http://homepage2.nifty.com/npo_crc/siryou/siryou_jyorei.htm
以下 新聞記事から引用です
====================
「子ども基本条例」制定図る
茅野市 子育て支援で協働促進
(信毎朝刊平成23年9月14日 4面)
茅野市の柳平千代一市長は13日の市議会9月定例会の一般質問で、来年度中をめどに子育てや教育で市と市民が協働していくための「子ども基本条例」(仮称)の制定を目指す方針を示した。18歳までの子どもの成長や子育てを支援する「子ども・家庭応援計画」の制度的な支えとしたい考え。高校生や大学生らの意見も交え、具体的な中身を検討していく。
同市では、市と市民が協力して施策の企画・立案をし、市民組織が実践する「パートナーシップのまちづくり」を推進。協働の柱とする福祉、環境、教育の3分野のうち、教育分野に基本条例がないことから、制定を図ることになった。
県内では、県や松本市などで子どもの権利条例制定を目指す動きがある。柳平市長は基本条例に盛り込む内容として「子どもの権利に関する内容だけでなく、子育てを通じて親の成長も促したり、読書の普及を進めたりといった内容を総合的に検討する」としている。
県こども・家庭課は「子育て分野に関する基本条例ができれば、県内では珍しいのではないか」としている。
====================
新聞記事 引用おわり
茅野市のホームページより引用です
====================
「こども・家庭応援計画(どんぐりプラン)」
たくましい子ども、やさしい子ども、夢のある子ども
どんぐりプランの誕生
市民が主体となり行政と共に子どもをとりまく諸問題を考えるため、平成9年に福祉21茅野(茅野市の21世紀の福祉を創る会)の分科会として「子育て部会」が発足しました。そこでは、母子保健だけでなく、妊娠中から乳幼児期、学童期を経て18歳になるまで総合的に検討されましたが、福祉21ビーナスプラン(茅野市地域福祉計画)の計画書を提出するにあたり、学童期以降、とりわけ思春期を中心とした時期に対する議論の不足が指摘されました。
そこで福祉21ビーナスプラン策定後、改めて市民ワーキングが組織され、子育て部会、市民ワーキングの考え方を統合し、こども・家庭支援について議論する場として、平成13年に市民34名によって「子ども家庭支援計画策定委員会」が設置されました。 委員会では、行政と共に詳細な議論を重ね「地域ぐるみの子育て・子育ちを応援していくシステム」を構築することを意図として、平成14年に「地域教育福祉計画」である「こども・家庭応援計画(愛称:どんぐりプラン)」をまとめました。
計画の目的
この計画は、子どもが生まれる前から18歳になるまでを一貫して子どもとその家族の子育て・子育ちを応援していくために、生涯学習や学校教育、また保健、医療、福祉といった関連施策を総合的に実施し、掲げられた理念を具現化するために、計画的に推進していくことを目的としています。
計画の基本理念
たくましい子ども、やさしい子ども、夢をもつ子ども
子どもたちが、豊かな自然のなかでさまざまな体験をつみ、人と人との交流のなかでお互いの個性を認め合い、生きる力を育んでいくことを応援します。
様々な課題をもつ子どもや親・家庭には必要な支援をきめ細かく提供していきます。
生命が宿ってから青年期までを教育・保健・医療・福祉が連携して、継続的、総合的な支援をしていきます。
子育ての喜びや大変さを分かちあえるまちを作ります。そのために、地域の教育力を高め、地域の人々が相互に協力して支えていくことを大切にします。
茅野市こども・家庭応援計画(どんぐりプラン)の本編はこちらから
→ http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07010066/07010066.html
====================
全国のこども条例について 調べたい
国際NGO 特定非営利活動法人「子どもの権利条約総合研究所」
→ http://homepage2.nifty.com/npo_crc/siryou/siryou_jyorei.htm
条約についての動き (ハーグ条約・子どもの権利条約)
信毎に記事があったのをきっかけに、両条約を調べてみました。(条約というのは、簡単に考えると国際的な法律だと思っています。ふつうに法律というと、日本国内の法律で、条例が、県内限定の法律・・・素人考えですが・・;)
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)
2011年7月現在の加入国は86カ国
(ウィキペディアより)
日本は未署名ですが
2011年5月に政府が加盟方針をうち出し
国内法制との整合性調整等の条約締結へ向けた準備を開始しています
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
2009年5月現在 署名国数140 /締約国数193
参考:外務省HP
【人権・人道(児童)】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csec01/index.html
1989年11月20日 1959年に国連で採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、
児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)が国連総会で採択されました。
1990年9月2日 条約が発効
同年9月21日 条約日本政府署名(109番目) しかし、国会での批准承認は見送られました。
1993年8月 細川首相が衆議院本会議で条約批准承認案の再提出表明
1994年3月29日 子ども(児童)の権利条約批准の国会承認
同年4月22日 条約日本政府批准
同年5月22日 条約国内発効
1994年5月22日 日本国内で効力が発生しました。
また、子どもの権利条約44条の報告審査義務に従い、日本政府は外務省が中心となって作成した報告書を
「児童の権利に関する委員会」に提出しています。その際、同委員会は、審査の精度を増すために、国内NGO団体などにもカウンターレポートの提出を求めています。
日本では、日本弁護士連合会、子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会、子どもの人権連、の3団体がカウンターレポートを提出しています。
1998年5月27日及び28日 日本の第1回定期報告が審査され最終見解が採択されました。
2002年5月5日~7日 国連子ども特別総会開催(ニューヨーク)
2004年1月28日 日本の第2回定期報告が審査され2004年1月30日最終見解が採択されました。
次回は2006年5月21日までに3回報告をするよう求められました。
2008年4月22日 外務省は第3回政府報告書を国連に提出。
2010年5月27日 日本の第3回定期報告が審査され(予定から約2年遅れ)6月11日最終見解が採択されました
第4・第5回をあわせた定期報告を2016年5月21日までに提出するよう求められています。最新のコア・ドキュメントを提出するよう求められています。(コア・ドキュメントがどんなものか、検索しましたが見つかりませんでしたm(_ _)m
以下、新聞記事の抜粋です
~~~~~~~~~~~~~~~
ハーグ条約加盟国問題で米次官補「進展がなければ日米関係悪化も」
(平成23年9月5日信毎朝刊 第二面)
【ワシントン時事】キャンベル米国務次官補(東アジア・太平洋担当)は4日までに時事通信と単独会見し、国際結婚の破綻に絡む子の連れ去り問題について「日米関係の主要課題になっている」と表明、「日本で問題が広く認識されていない」と懸念を示すとともに、早期に進展がなければ。両国関係悪化につながる恐れがあると警告した。
米政府は、日本人の母世やが米国籍を持つ子を配偶者に無断で日本に連れ帰るケースが相次いでいることを重大視。事件解決の手続きを定めたハーグ条約への早期加盟を迫ってきた。日本政府は5月に条約加盟国の方針を決めたが、これまでのケースへの対応では進展がない。
(以下略)
<解説>ハーグ条約 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の通称。一方の親が16歳未満の子を不法に国外へ連れ去り、残された親から申し立てがあった場合、加盟国は原則として元の居住国に子を返還する義務を負う。1980年のハーグ国際私法会議で採択され、83年に発行。現在84カ国が加盟している。日本政府は今年5月、条約加盟の方針を決定した。
~~~~~~~~~~~~~~~
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)
2011年7月現在の加入国は86カ国
(ウィキペディアより)
日本は未署名ですが
2011年5月に政府が加盟方針をうち出し
国内法制との整合性調整等の条約締結へ向けた準備を開始しています
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
2009年5月現在 署名国数140 /締約国数193
参考:外務省HP
【人権・人道(児童)】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csec01/index.html
1989年11月20日 1959年に国連で採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、
児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)が国連総会で採択されました。
1990年9月2日 条約が発効
同年9月21日 条約日本政府署名(109番目) しかし、国会での批准承認は見送られました。
1993年8月 細川首相が衆議院本会議で条約批准承認案の再提出表明
1994年3月29日 子ども(児童)の権利条約批准の国会承認
同年4月22日 条約日本政府批准
同年5月22日 条約国内発効
1994年5月22日 日本国内で効力が発生しました。
また、子どもの権利条約44条の報告審査義務に従い、日本政府は外務省が中心となって作成した報告書を
「児童の権利に関する委員会」に提出しています。その際、同委員会は、審査の精度を増すために、国内NGO団体などにもカウンターレポートの提出を求めています。
日本では、日本弁護士連合会、子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会、子どもの人権連、の3団体がカウンターレポートを提出しています。
1998年5月27日及び28日 日本の第1回定期報告が審査され最終見解が採択されました。
2002年5月5日~7日 国連子ども特別総会開催(ニューヨーク)
2004年1月28日 日本の第2回定期報告が審査され2004年1月30日最終見解が採択されました。
次回は2006年5月21日までに3回報告をするよう求められました。
2008年4月22日 外務省は第3回政府報告書を国連に提出。
2010年5月27日 日本の第3回定期報告が審査され(予定から約2年遅れ)6月11日最終見解が採択されました
第4・第5回をあわせた定期報告を2016年5月21日までに提出するよう求められています。最新のコア・ドキュメントを提出するよう求められています。(コア・ドキュメントがどんなものか、検索しましたが見つかりませんでしたm(_ _)m
以下、新聞記事の抜粋です
~~~~~~~~~~~~~~~
ハーグ条約加盟国問題で米次官補「進展がなければ日米関係悪化も」
(平成23年9月5日信毎朝刊 第二面)
【ワシントン時事】キャンベル米国務次官補(東アジア・太平洋担当)は4日までに時事通信と単独会見し、国際結婚の破綻に絡む子の連れ去り問題について「日米関係の主要課題になっている」と表明、「日本で問題が広く認識されていない」と懸念を示すとともに、早期に進展がなければ。両国関係悪化につながる恐れがあると警告した。
米政府は、日本人の母世やが米国籍を持つ子を配偶者に無断で日本に連れ帰るケースが相次いでいることを重大視。事件解決の手続きを定めたハーグ条約への早期加盟を迫ってきた。日本政府は5月に条約加盟国の方針を決めたが、これまでのケースへの対応では進展がない。
(以下略)
<解説>ハーグ条約 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の通称。一方の親が16歳未満の子を不法に国外へ連れ去り、残された親から申し立てがあった場合、加盟国は原則として元の居住国に子を返還する義務を負う。1980年のハーグ国際私法会議で採択され、83年に発行。現在84カ国が加盟している。日本政府は今年5月、条約加盟の方針を決定した。
~~~~~~~~~~~~~~~