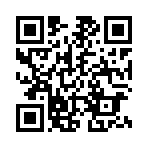子ども条例の制定を求める要望書(第2弾)提出開始です
子どものびのびネットワークでは、平成24年7月20日(金)に、長野県の子ども条例制定を求める要望書を県知事と、健康福祉部こども家庭課へ提出しました。
この要望書は、子ども尊重の条例制定に盛り込んで欲しい内容について、現場で子ども支援を行っている団体の声を草の根で集めた条例案です。
要望書・条例案への賛同メッセージはひきつづき募集していきます。子ども尊重の輪が広がっていくことを願っています。
お問い合わせはブログ管理人のメッセージ欄か、要望書の末尾連絡先へお寄せくださいm(_ _)m
===以下、要望書===
続きを読む
長野県への申し入れ書を提出しました(12.24一部修正)
3連休の直前ですが、「子どものびのびネットワーク」でつくった長野県への申し入れ書を、上條事務局長が県庁に提出に行ってきました。
語句の間違いがあり12月24日に一部訂正しましたm(_ _)m。
申し入れ書というのは、『市民の団体が、こういう行政をぜひやって欲しい』ということや、『行政の改善点を考えてもらう』ために作るもので、要望書とも、似ています。
どんな回答になるのか、祈るような気持ちです。
======以下、申し入れ書の本文です=======
平成2011年(平成23年)12月22日
長野県
知事 阿部守一 様
子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会
委員長 喜多明人 様
子どものびのびネットワーク
代表 佐藤芳嗣
(連絡先は、末尾のとおりです)
要望書
第1 要望の趣旨
1 長野県及び「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」(以下、「委員会」といいます。)が、子どもの権利を保障する実効的な仕組みを作るためには、子どもが育つための行政上の諸施策や社会資源が十分に整備されているかどうかを調べ、整備されていない部分については、具体的な整備目標を定めた上で、実現に向けて取り組んでいくことが重要です。
そこで、私たち「子どものびのびネットワーク」は、次の4点について統計などの資料や研究を、委員会が調査検討するよう要望します。
記
(1) 長野県内の学校に配置されているスクールソーシャルワーカー(:学校外の福祉、医療などの支援機関と連携して子どもの相談に対応している)の必要数は何人でしょうか。配置実態とあわせて調査してください。
(2) 発達障害などをかかえた子どもたちが健やかに成長発達することを支える機関として、長野県内の児童精神科医その他専門職による相談窓口はどれくらい必要でしょうか。資源実態とあわせて調査してください。
(3) 虐待や貧困など複雑な家庭背景を抱える子どもたちを支えている児童養護施設や里親の受入れ態勢は十分でしょうか。
(4) 子どもへの深刻な権利侵害である性暴力について、長野県内における子どもへの性暴力、また、子ども同士が加害者被害者となる性暴力の実態を把握してください。
2 長野県及び委員会が「子どもの権利条例(仮称)」の制定を目指して活動していることについて、「委員会つうしん」の発行だけではなく、子ども・大人を含めた県民全体に伝わるよう、わかりやすい広報活動を行うことを要望します。
3 長野県及び委員会が、県民と子どもの参加できる仕組みで委員会の話し合いを進めていくことを要望します。また、当「子どものびのびネットワーク」が長野県および「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」と懇談できる機会を設定されるよう要望します。
第2 要望の理由
1 はじめに
長野県では、今後3年以内に「長野県子どもの権利条例(仮称)」を制定することを目指して「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」を設置し、子どもアンケート調査を実施しています。このアンケート調査によって得られた結果は、長野県内の子どもが置かれた状況を把握する上で参考になると考えられます。
ところで、子どもたちが自身の権利を理解し、周りから尊重され、そして、のびのびと発達して他者の権利を尊重できる大人に成長するためには、我々大人たちが子どもの目線に立って子どもの権利を守ろうとする意識を醸成していくことが必要です。
しかし、それだけではなく、子どもの権利が守られるための行政上の諸施策や社会資源が十分に整備されていることもまた重要なことです。
2 要望の趣旨1について
長野県及び委員会として、長野県内の行政機関や社会資源が子どもの権利を保障できるものとなっているかを把握する必要があると考えます。その場合、長野県が把握している統計や指標の資料のみならず、他の行政機関や研究機関、あるいは民間が保有している資料も参考にしながら諸施策や社会資源の充実の目標を設定する必要があります。
私たちのびのびネットワークに県内各地から集まった会員で議論した中では、少なくとも次のような点を調査する必要があると考えました。しかし、他にも調査項目は多数存すると考えられますので、これだけに限らず他分野にわたり調査することを要望致します。
(1) 委員会に提出された資料によれば、平成22年の不登校児童数は小学校で498人、中学校で1757人ですが、そのうち親子関係をめぐる問題が原因に挙げられた児童が小学校で114名(22.9%)、中学校で172名(9.8%)います。その他の項目も併せ、家庭が大きな要因であると学校が把握している子どもが多数います。
また、県内5箇所の児童相談所では、児童虐待へ対応した件数が平成22年では839件ありましたが、そのうち施設入所となったのは90件、里親委託となったのは3件で、虐待を受けた子どものうちの9割近くは、親元で地域の中で暮らしていく状況とのことです。
いずれも、家庭への連携した支援が必要とされている現状を示していると考えます。現在の学校には学校内だけで解決できない悩みを抱えた子どもが多数在籍しており、その対応策としてスクールソーシャルワーカーを充実させることが重要であると考えますが、現在の状況で十分といえるでしょうか。
(2) 平成22年の長野県教育委員会の調査では、発達障害(LD,ADHD,広汎性発達障害等)の診断や判定のある児童数は小学校で2686名(2.19%)、中学校で1109名(1.8%)とのことです。さらに、診断等は無いが支援が必要ととらえられている児童生徒数が小学校3126名、中学校で999名います。医療機関への相談を求める親子も多いと思いますが、長野県内の児童精神科医その他専門職による相談窓口は十分でしょうか。
(3) 児童養護施設では子どもの権利を守るため、子どもの「安心」、「自信」、「自由」を守るCAPプログラムを導入し、相談できる体制づくりを進めている施設もあります。しかし、子ども達が抱えている様々な重荷を解決し、育ち直しをしていくニーズに十分対応できる体制にはまだ届かないのではないでしょうか。
今年3月と11月には、乳児3人を預かって保育していた家庭福祉員(保育ママ)宅で乳児の死亡事故が起きています(それぞれ横浜市と東京都)。児童養護施設や乳児院での人手は必要数を満たしているのでしょうか。夕方から夜間など、一人で何人くらいの子どもを見ている現状なのでしょうか。また、家庭的な環境で子どもを育てる里親制度を必要とする子どもたちはどれくらいいるのでしょうか。
(4) 弁護士活動や、子どもからの電話でSOSを受けるチャイルドラインの活動、直接学校などの現場に出向き子どもから相談を受けるCAPの活動などを通して、子ども同士の性暴力、子どもへの性暴力には深刻な実態があると感じています。長野県内における子ども同士の性暴力、子どもへの性暴力の実態はどのようなものでしょうか。この調査には、警察に問合せをすることを検討する必要があると解されます。
3 要望の趣旨2及び3について
子どもたちが自身の権利を理解し、周りから尊重され、そして、のびのびと発達して他者の権利を尊重できる大人に成長するためには、我々大人たちが子どもの目線に立って子どもの権利を守ろうとする意識を醸成していくことが必要です。
そのためには、子ども自身も、県民一人ひとりも、子どもの人権について理解し、意識を高めていくことが大切です。
委員会が「委員会つうしん」を発行していることは重要ですが、さらに子ども達にもわかるように活動状況を県民に知らせ、本件の重要性を周知していただきたいと考えます。また、当子どものびのびネットワークは長野県及び委員会と懇談する機会を持ちたいと希望しておりますので、よろしくお願い致します。
連絡先
〒390-0861長野県松本市蟻ヶ崎一丁目1番52号
子どものびのびネット事務局長
弁護士 上條 剛
TEL 0263-34-4466
FAX 0263-34-4467
======以下、申し入れ書の本文です=======
よろしかったらフェイスブックボタンに一票?お願いします 。
。
子どものびのびネットワーク 10月17日18時~
 子どものびのびネットワーク
子どものびのびネットワークミーティングは次回10月17日(月) 18:00~
長野県弁護士会館会議室
興味のあるかた、一緒に行きませんか? メールください(^^)
子どものびのびネットワーク に参加しませんか
長野県内で子どもと共に活動し、子どもの支援をしている方。関心のある方に呼びかけています。
子どものびのびネットワークでは、長野県がめざしている「子どもの権利条例」づくりの動きについて学び、発信しています。国際条約である子どもの権利条約に則った内容の条例の制定を目指しています。
 まなぶ (ミーティング)
まなぶ (ミーティング)・子どもの権利条例について学習会を企画しています
・県の委員会でどんな話し合いが行われているか学んでいます
 つたえる
つたえる・子どもたちの現状や、子育て・子どもの育つ環境への思いを語り合い、まとめて、発信しています
・県の「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」委員になっている当会のメンバーを通じて、話し合いへの情報提供をしていきます
 つながる
つながる・いろんな地域のいろんな子ども達の声が、ちゃんと県に届くことが大切と考えています
・子どもに日々かかわっている大人がつながっていくことで、子ども達に対して責任ある条例づくりをめざします
子どもの支援Q&A(データや計画の引用は長野県のHPより)
Q:「条例」や「基本計画」と私たち(県民)はどんな関係があるの?
今までの例では、「長野県男女共同参画社会づくり条例」がH14年12月に県議会で可決されました。女性の教頭先生が多くなったり(H17年17.8%→H20年20.5%※小学校)、県内の各自治体でさまざまな事業が行われるようになりました。「長野県障害者プラン(後期計画)」はH19~5年間実施。グループホーム、相談窓口を増やすなどの目標が作られ、実際の達成数値が公表されています。
法律(条例も法律)や基本計画は公共の仕事の方向性、目標設定となるため、子どもの育ちに本当に必要なことは条例に盛り込まれることが大切です。計画、根拠法で方向性が一度決まると、場当たり的ではない事業が展開されていきます。
Q:子どもへの支援について、県ではどんな部署でやっているの?
基本構想として「新たな総合5ヵ年計画(企画部)」「長野県子ども・若者計画策定(企画部次世代サポート課)」「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会(健康福祉部こども家庭課)」が始まっています。「長野県教育振興基本計画(教育委員会)」は5ヵ年計画で、来年度が総括の年です。
行政機関は複雑に役割分担され、外からはどこに相談すると前にすすむのかわかりにくいです。でも、実際の子育ては妊娠期から大人になるまでエンドレスで待ったなしですよね。年齢区分を超え、部署のタテワリも超え、子ども達を包み込むような支援が必要とされているのです。いろんな地域のいろんな子どもたちの声を受け止め、子どもを支援する大人たちがヨコワリで集まって、ネットワークしていくことが大切です。
<こどものびのびネットワーク今までの活動>
「子どものびのびプロジェクト -子どもの参加とその支援を考えるー」シンポジウム 実施(H23.5.6)
喜多明人先生の学習会を開きました
テーマ 「子ども支援のまちづくり」と条例」
(子どものびのびネットワーク学習会 平成23年7月24日)
会場:長野県弁護士会館 参加費:カンパ
※ いち参加者による自己流まとめです
それぞれのフィールドから集まった参加者が車座で喜多先生と学びを深める会となりました。
<喜多明人先生講義>
テーマ:「子ども支援のまちづくり」と条例
喜多明人氏・・・早稲田大学文化構想学部教授。もともとは学校建築が専門。まちづくりや子どもの権利に取組んでいる。
活動:子どもの権利条約ネットワーク事務局―シンクタンクのような活動をしている。
今回、長野県「子どもの育ちを支える仕組みを考える委員会」委員長となる。任期3年。
概要:
1:子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会の立ち上げとこれから
2:いま、子どもたちは―直面する課題
3:なぜ、子ども支援なのか
4:なぜ、まちづくりなのか―子どもと「共に生きる」まちをつくる
5:なぜ、条例なのか
6:質疑応答
<喜多先生講義>
1:子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会の立ち上げとこれから
続きを読む
子どものびのびネットワーク に参加しませんか
長野県のこどもが、「安心して」「自信を持って」「のびのび」育つことを願って「こどもの参加」と「こどもの支援」に取り組むおとながネットワークしています。
子どものびのびネットワークでは、長野県がめざしている「子どもの権利条例」づくりの動きについて学び、発信しています。国際条約である子どもの権利条約に則った内容の条例の制定を目指しています。
個人の自由参加・立場を超えてのボランティア活動です。さぁ、あなたも今日から・・・
★ まなぶ (プロジェクト会議)
子どもの権利条例について学習会を企画しています
県の委員会でどんな話し合いが行われているか学んでいます
★伝える
子どもたちの現状や、子育て・子どもの育つ環境への思いを語り合い、まとめて、発信しています
県の「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」委員になっている当会のメンバーを通じて、話し合いへの情報提供をしていきます
★つながる
いろんな地域のいろんな子ども達の声が、ちゃんと県に届くことが大切と考えています
子どもに日々かかわっている大人がつながっていくことで、子ども達に対して責任ある条例づくりをめざします
事務局は長野県弁護士会内におかれています
関心がある方はコメント欄またはyokowari@facebook.comへお問い合わせいただければと思います。
(facebookのメールは始めたばかりでちゃんと届くか、ちょっと自信がありません(・・(;)
規約・入会申し込みは「子どものびのびネットワークチラシ」をご参照ください
ヤフーボックス内に公開中です→ https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-j5zgfh3drsk2cbxgx2jho7fcju-1001&uniqid=ba665320-00ad-451c-b01b-54f2fe507f0d&viewtype=detail
★★子どものびのびネットワーク今までの活動★★
「子どものびのびプロジェクト -子どもの参加とその支援を考えるー」シンポジウム 実施
(H23.5.6)
「子ども支援のまちづくり」と条例に関しての勉強会」 講師:早稲田大学喜多明人教授 実施
(H23.7.24)
不定期ですが、随時学習会、話し合いを行っています。
はじめに ~このブログについて~
ありがとうございます。 管理人のusiki@篠ノ井ですm(_ _)m
*このブログは
・管理人が参加しているボランティア団体「子どものびのびネットワーク」の活動に関することの発信
・子どもの育ちと、子ども支援に関する情報
・管理人が勉強中のことの記録(自己流)
・ワーキングマザーとしての日々のつぶやき
が中心となっております
*このブログのお願い
・管理にかける時間が少ないため。お問い合わせにお答えするにはお時間をいただきたいのです。
・トラックバック、コメントは認証制にしております。コメントでは迅速な対応ができませんので、内容によっては承認できないときもあります。話を深めたいような内容はできるだけトラックバックでお寄せいただければありがたいです。
・個人情報が入るコメントや、こどもの閲覧にそぐわない内容のコメントは承認できません。
・リンク掲載については事前に一度ご連絡ください。
・当方からのリンクを、直接お会いした方にはずうずうしくお願いするかと思います。どうぞよろしくお願いします。